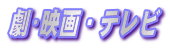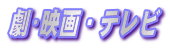|
★(映画)「HERO」
監督:鈴木雅之
出演:木村拓哉、松たか子、松本幸四郎、角野卓造、
大塚寧々・阿部寛、他
イケメン・タレントの印象が「武士の一分」でなくなった木村拓哉、お嬢さまのアイドルスターと考えていた松たか子の地味だが堅実な演技をいくつか見て偏見を感じなくなったこの頃、馬鹿にテレビで宣伝している、横文字タイトルの邦画を観た。「HERO」である。この所ばったりと途絶えていた久し振りの映画館行きとなったせいもあってか、すっかり感動して帰って来た。
僕の観るテレビドラマは殆どが推理サスやミステリーものだ。その中には検事側だった人間が、ある動機で別の職業に変わったり、弁護側の人間に代わって、事件の真理を追うというものが多いが、ここでは自由な気侭な生活態度のまま検事として、どんな小さな事件とも全力で取り組む若い検事(キムタク)が描かれている。担当の女性事務官雨宮(松たか子)との協力で、手探り捜査を粘り強く続ける。現在担当している事件はある結婚間近かの会社員がすれ違った時に相手の金髪の青年にいきなり撲り倒され、後頭部を強打して死亡するというものだった。運悪くこの事件は高名な政治家の汚職事件がらみのアリバイに利用され、この容疑者は公判途中で無罪を主張し始める。弁護を担当しているのは検事上がりの敏腕弁護士(幸四郎)でなかなか容疑を固めさせてはくれない。寸分のスキもない証拠を要求して来る。キムタク演ずる久利生検事はそれに誠実に対応し、確実な実証を求めて韓国まで足を伸ばす。雨宮がいつも傍にいて力になっている。最後には放火事件がらみの野次馬の中から彼ら担当の容疑者が写されている写真の存在に気付き800人以上の人に当たって、
遂に実証を探し当てる。最後の公判で、次第に信頼を得るようになった仲間たちの手によって証拠物件が持ち込まれた時の、久利生の力に満ちた弁論はまさに感激的である。検察庁の中に現存する、瑣末な刑事事件を担当する検事と大物政治家の汚職事件を捜査する「特捜」との差別感や、物のように送り込まれて来る容疑者達の取調べに次第に人間に対する姿勢を失い、冤罪を出しかねない現状に警鐘を鳴らしている。久利生はこの裁判で敏腕弁護士と誠実に「闘い」ながら、お互いの人間性を高め合うのだった。
こう書いてくると、深刻な映画のように思われる方が出そうだが、この監督は独特の映像処理と音の扱いのリズムを見せてくれる。タイトルが画面に出てくる前は、まるで予告編のように短いショットが、ジャズピアノのリズムで流され、登場人物は本のページの隅に書かれた手作り映画のようにピコピコと動く。鋭い音声を突然カットしてそれを繋いで行く。人の出入りも意表を突いているし、カメラもどこから狙っているか見当がつかない。時には上から落ちてくる。新しい楽しい表現である。是非ご覧下さい。
★(映画)「フラ・ガール」 監督:李相日
出演:松雪泰子、豊川悦司、蒼井優、山崎静代、
岸部一德、富司純子
女房に「何か良い映画やってない?」と言われて、ユーナイテッド・シネマのサイトを調べた。「出口のない海」「フラガール」「ブラックダリア」「涙そうそう」などがあったが「良い」は主観だから、最終決定は任せた。これが映画「フラガール」との出逢いである。ただテレビであのオスギが誉めていたので関心はあったのだが・・・。
僕はたかだか、この作品の監督の名前は知らない、藤純子が今は富司純子と言ってることも知らない、豊川でも名前と顔が一致しないと言う程度の「映画ファン」なのだ。李監督の作品を僕は始めて観たのだった。今まで俳優の力を見事に引き出す監督と言われていたそうだが、この映画では、キャスティングも優れているのだろうが、制作中に沢山の若い女優たちを育ててしまったのではなかろうか、いやベテランの俳優までを見事に磨きをかけてしまったのではないかと感動すら覚えた。
黒いダイヤと言われていた頃栄えていたイワキも、石油文明に押されて炭坑(ヤマ)そのものが成り立って行かなくなって来た頃の話である。炭坑町は灰色に寂れ、長屋も活気を失い、会社と組合は合意で大量首切りに合意するようになる。街の乗り切り策として、温泉を利用した健康レクセンターとして、「いわきハワイアンセンター」という観光施設建設という施策が浮かび上がり、実行される。困窮し苛立つ炭坑の家庭はどこも暗いが、地味な若い女性たちもフラダンスのダンサーへの養成を受けてプロの道を夢見、同時に生活の活路を見出そうとする。古い炭坑の保守的な大人の生活感覚では、若い娘達がフラダンサーとして転身することが、懸命な生き方の1つであるとは映らず、身を持ち崩す危機に映るのだった。
やがて迎え入れられて東京からやって来るダンスの先生は、若い女性たちには夢と新しい希望とを感じさせながらも、先生の若さと気風は最初はとてもこの環境には受け入れられない。村八分的な目にも遭うのだが、先生の一途な真面目さと美しい踊りの見事さで若い女性たちとはしっかりと結びついていた。娘達のダンスは次第に本物となり、いくつもの試練を越えて一人一人が先生を中心に生きる事の真剣さ、熱さ、辛さ、清々しさを身につけて行く。先生も指導者として、成熟した女として大きく成長して行くのだった。
産業構造の変化の中で起きてくる生活の危機を生き抜いて行く苦いが清涼な生き様をそしてその中での人間の成長を、フラダンスという熱い表現を媒介にして見事描き切っている。泣き上戸の僕には始末に負えない作品であった。李監督の過去の作品を見たいのは勿論今後に大きな期待を寄せたい。(2006・10・16記)
★(映画)「日本沈没」小松左京原作
大分前にも観たが、これは新しく映画化されたもので、キャストも草薙が主役。彼個人としては久し振りに纏まったものを観たが、かなり演技上の進歩が見られる。大柄なのにどこか繊細さが目立って、ナヨク見えていたが、コントロールの効いた良さが目立ち始めた。この手のパニックものには親子関係とか恋人関係に支えられて頑張る人間が出てくるのだが、現実の厳しさの重みでリアリティを失ってしまうことが多い。変わっていないのは、国家的な大事件なので、政治の中枢の動きや自衛隊の最新装備のご披露がされる所。しかし特撮技術が進み、火山の爆発、地殻の変動場面、津波の襲来などは、前回より遥かに凄まじく迫力がある。特に研究室や深海潜水艇の計器類を中心とした画像、海底の地殻を掘り下げマグマに達することが可能な穿鑿船の存在、巨大なエネルギー(核爆発か?)を利用した活断層の動きへのコントロールという戦略、そして破壊の進む日本列島の惨状を衛星撮影のような俯瞰図で捉える方法など、その描写力、表現力は遥かに強力になった。
しかしこのようなテーマは、問題によっては決して荒唐無稽なパニックではなく、かなりの科学的根拠のしっかりした問題である場合も多くなっていると思う。地震、津波など、地球汚染が進む中、決して架空な作り事ではないので、描き方、特に人間の描き方はしっかりとしたリアリティが要求されるだろう。
現実にこのような事態となれば、政府は研究者に緘口令を敷いて、真実をなかなか伝え様とはしないだろう。この映画でも1年以内には列島は沈没ということが明確になっているのに、国民には「5年」と発表する。パニックを防ぐためだ。しかし現実に真実はいろんな形でいくつもの流言蜚語を誘発し、不安は拡大して行くだろう。当然権力的統制は極端に強くなり、さまざまな大衆への抑圧の津波を引き起こすだろう。金持ちや要人たちの生命優先も起こり得るし、短時間の間に利己的な金の動き、輸送手段の独占化なども起こり、個人的な愛や、ヒューマニズムなどは、虫けらの様に踏み潰されて行くのではないか。最終的に指揮権を握った女性大臣が科学者との連携を取りながら、いろんな場所で指揮に当たっているのだが、研究所でも船の上でも、一般の避難した人々と同席をしていたり、実際にはとても考えられない場面も多い。ここでは草薙演ずるところの深海研究員の犠牲によって、一旦は仲間が失敗した爆薬投下を、潜水能力の劣った旧式潜水艇で再度の投下に成功し、一時的にしろ、断層移動を食いとめるという結末になるのだが、彼は明かに恋人と幼い孤児を愛するが故にこの行為を決意するのだが、僕などは昔教科書で習った「爆弾三勇士」を連想してしまうのだ。下手をすれば国民の犠牲のもとに日本を守るという愛国心鼓舞のドラマ版に見えて来る。愛の関係が素直に結び合う社会は、良い政治の元で始めて成り立つものなのだ。アイロニーとして面白かったのは、病気の牛肉まで無理矢理に輸入する事にした小泉路線のアメリカ追随にも拘わらず、この事件では要請されたアメリカの援護は極めて冷たくあしらわれる結果となるのである。ロマンスがらみで「場合によって生命以上に大切なものは、愛する人を守るための行動」であると訴えているが、人が人を自然に愛せる時、国が国民を愛する国家であるとき、国民は黙っていても「価値あるものを守るために」身を捨てて闘うものだ。それが自然な誇りというものだと思う。(2006・7・28記)
★(映画)「野性の夜に」1993公開・フランス映画
監督・原作・脚本・音楽:シリル・コラール
キャスト:ジャン=シリル・コラール; ローラ=ロマーヌ・ボーランジェ;
サミー=カルロス・ロペス; ローラの母=コリーヌ・ブルー;
ノリア=マリア・シュナイダー;
これまた図書館所有のビデオである。僕の全く知らない世界に住む青年の話しだが、人間という存在のあり様を押し広げ、驚きと痛みとをもたらすのに充分な作品である。
主人公は、エイズキャリアーを持ち、バイセクシュアルのカメラマン=ジャンである。青年のカメラと音楽に向かう生活は壮絶なくらいに無軌道な性的快楽で夜を迎える。自由な欲望がこのような形をとるということが僕には理解の出来ない世界である。彼が欲しいままに行動すると相手が男であろうが、女であろうが性の対象になりうるのだ。いわゆるホモという世界に居る男が何故同性の男を求めるのか、その内実は僕には所詮想像を超えるものでしかない。聞くところによれば、女性に対する嫌悪、軽蔑、場合によっては憎しみが原因の場合もあるし、常識的な性交、妊娠、家庭の営みと言うのを嫌うためとも聞く。日本にも「お小姓」というのあって、織田信長と森蘭丸、三島由紀夫と森田と言うような思想信条や主従の信義を軸にした性関係も存在した。男同士の精神的な同一感に基づく性関係なのであろう。それは性とは別なのではないかという疑念が僕には起こるが、当事者にしてみれば真剣な反常識、反体制(時代によっては体制内の暗黙承認の形)の生き様なのであろう。軍隊や監獄のような男だけ囲われた世界では性処理としての暴力的な関係の結果という場合は充分にあり得ることだ。しかしごく普通の世界では、男と女が存在している。その上で敢えて同性を相手に選ぶ真意というものは何なのだろう。自分の成育歴の中で身につけた女性に対する特殊な忌避意識。家族の営みに対する忌避意識なども考えられるが、現代では避妊の技術はそう難しい事ではない。
この映画の主人公は、男との関係、女との関係が平行して起こり得るのだ。しかも相手の若い女性は極端にホモ関係を嫌悪し、自分とだけの固定した愛情関係を強く求めている。しかもホモ関係を知っても離れてしまわず、懸命に彼をたち直らせようとする。彼はそれを「見苦しい独占欲」だとなじる。しかし彼女の命を賭し兼ねない迫り方に、次第に何かを感じ始めていたのではないか。愛というものの漠然とした輪郭が見えて来ていたのではなかろうか。現在自分が通過している関係とは異なった何かがありそうだと。しかしエイズが進行している彼は死への絶望感にも苛まれていた。
人間個人個人の性は、性器による分類とは別に、観念や行動志向性などに「男性」と「女性」というエレメントが連続的にその%を変えて存在していて、性的個性とでもいうものを作り上げており、自らの性衝動の質や求める相手はそれによって選択されるのではないか。勿論単なる好奇心や犯罪的な意図は別である。女性器を持った「男性」、男性器を持った「女性」、そして無数の中間的存在を夢想すると、妖しく咲き乱れるトロピカルなお花畑でも眺望している気分にもなる。勿論この作品はそんな悠長なものではない。主人公ジャックを演じ、この映画を全力を傾けて作り上げ、エイズのために35歳という若さで死んでいったシリル・コーラルは死ぬまで「これが愛なのか」という問題に煩悶していたに違いない。それを体をかけて問題提起したのは、自らも病魔の恐れに慄きながら彼を愛し続けた17歳の少女だったのだ。(2006・7・22記)
★(映画)「グラン・ブルー」 リュック・ベッソン監督
実はこの映画には奇妙な関わりを持つことになった。2週間に1度は必ず出向く市の図書館で借出したビデオなのだ。162分という記録があり、まずこの長さに注目した。説明からダイビング(いわゆる素潜り)の世界を描いたものであり、綺麗な絵にお目にかかれるだろうと期待したこと。だが、それにもかかわらずケースには「初めの部分に傷あり」と明記してあった。もともと「グレート・ブルー」という英語のタイトルのものを、フランス版にして1992年6月に劇場公開され、連日2時間待ちの大盛況を見た作品のようだ。「完全版」の中の「完全版」とされるこの作品には「グレート・ブルー」にはなかった49分の未公開シーンを付加したという。忙しい仕事に追われ、途切れ途切れに観たせいか、3分の2が終る頃までは左程僕の心を惹き付けなかった。しかし最後深夜に独りで観た残りの部分で、僕の評価はひっくり返った。そして淡々と描かれて来た前の部分がしっかりと鮮明に浮かび上がって来た。全体を見終わった時、この作品は、ここに紹介せずには居れない作品となっていた。
主人公はジャン=マルク・バールという俳優の演ずるジャックという青年。その兄貴分のエンゾ。そしてジャックの恋人ジョアンナ。この女性ジョアンナはロザンナ・アークエットという女優が演じ、実に美しく可愛らしい女性である。ジャックとエンゾは、ダイビングの世界的記録保持者であり、人間の限界に近い120メートルの深さまで潜れる選手である。二人は同性愛者かと思うほど親密な友情を通わせ、海を媒介とするこの結びつきを越える女性の存在は考えられない。イルカの群れが乱れ舞う海を人魚と戯れるように泳ぎ回る二人。特にジャックは海の動物たちにこの上ない優しい眼差しと微笑みを向ける。青から蒼へ、そしてさらに碧へと魅力的に変化する海の色。楽しみを超えて、自分を統御できなくなる程引き込まれる二人にとって、海は遊びの対象ではなく、生の対象であり、死の対象であり、哲学となって行く。女性への愛をも遥かに超えている。その意味で懸命にジャックを愛するようになったジョアンナが憐れなくらいである。海は母であり、女性を超えた「性」であり、その海深く潜ることの意味をジャックは「帰って来る必要を感じないもの」と表現する。
最後は、二人とも旅に出るように海の底へと姿を消して行く。ジャックには妊娠を告げられた恋人ジョアンナが居るにもかかわらず・・・。僕が知らないのに、畏敬と畏怖の念で憧れる何かが、この二人を連れ去ったと思われるのだった。(2006・7・15記)
★(映画)「明日の記憶」 渡辺徹・樋口可南子主演
若年性アルツハイマーに冒された働き盛りの会社員一家の記録である。渡辺自身がエズゼクティヴ・プロデユーサーの役にあることからも、彼の思い入れの強い作品なのだろう。多忙な勤務のストレスの中で、次第に苛立ちの日々が多くなり、もの忘れが目立ち、それがやがては会議の日程を忘れるような勤務に係わる現象となって行く。病状の進行は恐ろしいくらいに速い。廻りの社員には「奇行」と映るようになる。当然上役にも、関連会社の幹部にもそのことは伝わるようになって来る。本人は頑張りたいという気持から、病気を隠しているが、やがて隠し切れなくなる。かかっている若い医者に対する抗いも、見苦しいくらいに惨めだ。ついに依願退職となり、自宅で静養するが、替わって働きに出るようになった妻との生活が、病的にギクシャクし始める。妻も生活を守り、何とか夫を立ち直らせるために懸命であるが、記憶喪失の進行する夫は、帰宅時間の遅れる妻に惨めな嫉妬をぶつけ、争いが繰り返される。手先を使う運動が良いと昔やった陶器の製作に通うが、それさえもままならぬ状況に至る。夫は自分でも施設に入らねば妻にも迷惑をかけるだけだという意識が強まり、自分から介護の施設見学に訪れもする。施設の人からは「奥さん(患者本人)と会ってみないと細かなことは言えない」と勘違いされたり・・・。想い出の場面が現実と錯綜して幻覚の形で現れ、主のいなくなった窯で一晩野焼きの真似事をして過ごす。家出同然であり、翌日妻に連れ戻される。介護施設に入った彼は椅子に座って一点空を睨んだままである。
この映画は、良くある「夫婦愛情物語」ではない。社会の仕組の中で、ストレスが働き盛りを襲い、記憶を、脳を蝕んで行く現実がいかに家庭を家族を追い込んで行くかを物語っている社会ドラマである。舞台が身近な渋谷であり、主人公の仕事が、その街のイメージ創りに関わる会社なので、見ていても極身近なことに感じられる。改めて、これは決して稀有な出来事ではないぞ、という気持になって来る。(2006・6・15記)
★(映画)「時計じかけのオレンジ」
何とも象徴的なタイトルである。カラクリ仕掛けで平和な優しさを湛えるオレンジはいかにもシュールなイメージだ。猥雑とも言えそうな道具立てが次々と設定され、特殊な隠語を駆使する暴力若者グループの殺し合いの抗争、女性をレイプする男たち、集団的老人イジメをするチンピラども。バックに流されるヒットラーとナチ軍の映像などが暴力の構図として展開されて行く。やがてその中のリーダー格アレックスの姿が浮かび上がってくる。残忍非道な青年の存在は、近未来における現代の悪の構図のエッセンスとなっている。
やがて国家機構は、彼を捕えることになるが、その国家権力の末端もアレックスに負けない暴力的な振る舞いの集団である。これが「基本的な人権」を重荷とする現代の警察の未来図なのかと唖然とする。カウンセラーの先生までが、同じような姿で描かれる。
彼は刑務所で再教育を受け、ある警察所属の牧師の世話になり優良囚人として遇される。法務大臣の査察の際に、所内でも噂になっていた特殊な「更正処理法」なるものの実験台になることをアレックス自身が志願する。大臣は特に彼を推薦し、完全な善人になるべく、実験病棟へと移される。眼をこじ開けられたまま、残虐な記録映画を見続けさせられ、脳や神経にも処理を与えられる「改造処理」を受けて、遂にはどんな屈辱にも怒りを燃やすことなく従順に対処する「人間」に改造されてしまうのだ。
やがて退院した彼は、このような人権無視の「更正処理法」を進める派と、それに反対する派との抗争に巻き込まれ、双方から利用されそうになる。いずれの側からも、彼は抗争の道具でしかない。改造過程で、彼はもともと好きだったベートーベンの第9交響曲が利用されたため、怒りと暴力行使への欲求が高まると、気分が悪くなり吐き気を催すようにされていた彼は、退院後奇しくもかって襲った老人や作家や女性と出会い、今度は彼を恐れ、復讐の炎を燃やす対象とされ、その都度、得体の知れない不快感に苛まれるのであった。そして「処理法」に反対するグループの手に保護されて、治癒のための処置を取られるのだが、正常な感情を取り戻す過程でもまた彼は感情の変化の度に苦痛に悩まされ、好きな音楽を聴く度に死ぬ思いを繰り返すのであった。
社会構造の力のバランスで、どうにでも作り替えられ、苦悩から解放されることのない哀れな若者アレックスに僕は進行する現代の若者の姿をダブらせて、この気味の悪いシニカルなオトギバナシに心を震わせたのだった。正常な怒りとその暴力による表現が人間性の本質とどう関わるのか。現代における深刻なテーマでもあるのだ。(2006・4・28記)
★(映画)「ピアノ・レッスン」
今頃何だ、と言われそうだが、タイトルだけは聞き及んでいたが、観たのは初めて。例によって俳優の知識はないので、その辺は何とも言えないが、映画としてかなりの好作品だと思う。引き攣ったように表情の硬い女性エイダが9歳の娘フロラとピアノと共に船で海を渡り、密林の開拓地のような所で暮らす事業家らしい男の所に嫁いでくる。顔も始めて見る男のようだ。浜辺に下ろされた家財道具の中で、運搬が困難なピアノだけが、波打ち際に取り残され、その光景は一種のポエジーをそそる。新妻は雷事故で音楽家の元夫を失い、自らは言葉を発する事が出来なくなった。娘を媒介に手話のみが伝達手段となっている。新しい夫のピアノに対する処置から、初めて会う妻がピアノを弾く事のみで、自分の情感を表現しているのが理解できないことが分かる。額に刺青を施したベインズという現地の男の土地と交換に海岸のピアノを売り渡してしまう。条件として妻はベインズにピアノのレッスンをしなければならない事になり、彼の家をしばしば訪問することになる。ベインズは、彼女への関心を深め、ピアノを引くエイダを愛するようになり、夫に代わってピアノの音を彼女に与えたベインズを、エイダもまた愛するようになり、不倫の関係が出来あがって行く。夫も彼女を愛し、愛されたいと思っているが、ピアノを無視したように、彼女の気持の琴線に触れる事も出来ずにいる。しかし彼女とベインズの関係を知るに及んで、強烈な嫉妬を燃やすようになり、ある日二人の交情場面を目にして彼女への執心とベインズへの憎悪が膨らむ。
エイダが「私の心はあなたのものよ」という恋文を娘を使ってベインズに届けさせようとした時、娘はそれを「悪い事」だと察して、手紙を夫に届けてしまう。怒った彼は妻を捉え、鉈で指を一本切り落としてしまう。そして、今後は二人が逢引きをする毎に、指を1本ずつ切り落として行くと娘を通じてベインズに伝えさせる。エイダの身を案じているベインズは、友人に強い憎悪を燃やす。二人の衝突は頂点に達しそうになるが、夫スチュアートは、銃を手にしてベインズの前に出ても、友人の顔を目にすると、態度が変わってしまう。スチュアートは、「お前だけが彼女を救える」と言って、二人でこの地を離れる事を約束させる。エイダとベインズはまた娘とピアノを乗せた小船で海に漕ぎ出すが漕ぎ手たちに警告されていた通り、船は安定さを欠き、転覆の危険がはっきりして来た。エイダは、ピアノを海に棄てることを申し出る。ベインズは反対するが、結局結んだ綱を切ってピアノを海に投棄することになる。船は激しく揺らいで、ピアノを海に吐き出すが、何とピアノは綱でエイダの脚にしっかりと結びつけられていた。ピアノとの心中を彼女は意図していたのだった。ピアノの重さで海中深く沈んで行くエイダ。苦しい表情の中で、突如彼女はピアノを裏切って、ピアノを振り解いて、海上へ。危うい所を船人たちに助けられ、ベインズの元で息を吹き返す。愛着のピアノを棄て、瞬間的にベインズとの生を選択したのだった。
新しい住処で、ベインズが作ってくれた義指を嵌めてピアノを教える彼女の表情はすっかり落ち着いていた。ベインズの愛に包まれたエイダは、海に沈んで行く時のあの旋律と、「生きよう」と決断したあの時間を忘れる事はなかった。
ピアノ、海という道具立ても、描き方も、音楽も言い知れぬ甘美なポエジーに包まれていた。しかし、性的な描写は、それを壊しかねないエロチシズムに溢れている。リアリズムとリリックな世界との際どい融合である。性をもっとリリックに描けなかったかとも思うが、これを詩のエッセンスで仕上げるのなら、エイダはあのままピアノと共に海に沈み、ベインズの元に戻らなければ良かったのかもしれない。最後に特記したいのは、子役の素晴らしい演技と、この役柄こそ、この作品のリアリティを支える極めて重要な存在であることだ。
(2006・4・26記)
★(映画)「四月の雪」と「蝉しぐれ」
しばらく途絶えていた映画鑑賞。妻が観たがっていた「四月の雪」に付き合ったら、映画館の大画面の味を思い出し、立て続けに「蝉しぐれ」も観に行く事となった。会員証のポイントも溜まっていて、1本は無料で観られた。
「四月の雪」は、いわゆる「ヨンサマ」の韓国映画だ。テレビドラマで韓流が流行り出した頃から、僕は長ったらしくメソメソしている手法に馴染めなかった。兄弟愛を描いた戦争ものなどの映画作品にはとても感動して、韓国映画は今後注目!と思っていた僕なのだが、家族制度がらみのメロドラマとなると、どうもついて行けなかった。この映画もテーマは、それぞれ夫と妻に愛を裏切られた男女がそのショックで不倫の愛に入り込むという単純なストーリーなのだが、いかにもグジュグジュと長ったらしく、超スローのテンポで描かれる。
交通事故を起こして病院に運ばれた男女は不倫の仲で、やがてそれぞれの妻と夫が病院に駈け付けてくる。次第に事実が分かって来ると、失意に落ちた二人はそのやりきれなさを言葉少なに語り合い始める。ダブル不倫は「ダブル復讐」から「ダブル癒し」へと雪崩れ込んで行く。二人は入院中のそれぞれの連れ合いの看病をしながらも次第に心を寄せ合い、ついに肉体的にも結ばれるようになる。やがて事故の男の方は死亡するが女は回復し、意識を取り戻して夫との会話ができるようになる。出会った女は孤独となり、出会った男には、車椅子の妻の世話が待っている。四月が好きな男と雪が好きな女は、珍しく雪の振った四月のある日車で目的の見えぬ旅路に就いた。ここで映画は終わっている。
テーマよりも何よりも僕はそのテンポの遅さに辟易した。日本人も「間」を重んじる美学を持っているし、沈黙の表現力、距離を持った感情の密着など大好きな民族だが、この粘っこい超スローテンポには、すっかり「イレテ」しまった。しかも「日本人向きにテンポを速めた」という監督談話を知って、さらに唖然としたのだった。
しかし、ゆったりとした座席で観る大画面の壮快さを思い出した僕は、またまたユナイテッドシネマ入間へと足を運んでいた。今度は邦画「蝉しぐれ」である。前にテレビドラマで観たことのある話の映画版なのだが、市川染五郎と木村佳乃のコンビが好演している。監督は黒土三男なので、安心して観ていたが、いつもテレビドラマの演出で見せる厭きさせない手法が充分活かされていない感じがした。「おふく」の幼少時代から「出世」してしまった「おふく様」へのイメージの繋がりが、どうもすとんと僕の胸には落ちてこないのだ。その点はテレビドラマの方が成功していたのではないか。おふくの子供を連れ去る下りは、さすがに迫力があったが、一つ一つの見せ場の流れの必然性が説明不足だと思う。特に文四郎とふくの愛の芽生えの部分は、演技不足のせいもあるのか物足りなかった。
「四月の雪」でテンポが気になっていたせいか、「蝉しぐれ」を見ながら、いつも「テンポ」を気にしていた。「お茶漬けの味」に代表される小津監督の映画などの「間」が外国人には正しく伝わっていないのではないか、と不図思った。動きと「間」の創り出す人間の行動テンポは、生活環境や職業によっても異なってくるだろうが、民族的な違いもあるのかもしれないなどと考え考え、帰途についた。
★(舞台)「八月に乾杯!」 ねりま演劇を観る会8月例会 劇団俳優座公演
アルブーゾフ作・袋 正訳・演出
8月30・31日にやったものだが、記述が遅れてしまった。海辺に近い保養地で女性患者と老医師が出会い、始めはぶつかり合う個性だったが、徐々に興味は膨れ上がり、恋らしきものへと発展する。医師ロジオン(小笠原良知)65歳と、もとはサーカスに居たという患者リーダ(岩崎加根子)60歳。二人には悲しい戦争の傷があったのです。ロジオンには自分と同じ外科医で、従軍地で戦死した妻が居た。リーダには同じ戦争で亡くした息子がいたし、夫は別の女を作った。見栄と作り話で取り繕っていたが、心を許し始めた二人は、本根の相互理解へと近付き、相手が戦争の深手を負っていることに気付き始める。誰もが自分の惨めさを人には語りたくないものだ。同じ運命を余儀なくされたことを知り、二人の接近は一層早まる。別れが近付いている事を自分に強いながらも、分かれがたい二人。立ち去ろうとしていたリーダも、戻って来てしまうのだった。
二人芝居は正味120分に及ぶ。IMAホールは小ステージである。これが練馬の大ホールだったら、上演しなかったかもしれないし、しても好評は得られなかったであろう。動きの少ない微妙なセリフの面白さだけで展開されるこの芝居はセリフが命だ。観客と二人の心の距離をどれだけ縮めるかが、芝居の成否を握っている。演出も心を砕き、緞帳も使わず、いつ芝居が始まったかも定かでなく、小笠原が紙飛行機を飛ばして、観客と戯れる所で、徐々に芝居は始まるのである。二人のセリフは会話でありながら、観客への語りでもある。幾つになっても、自分の人生は明日から始まるのだという楽観主義は、多くの会員には
「夢」と映った様だ。「あれはお話だけど・・・」といいながらも「でも元気出さなけりゃね」と笑う。そんな運命が自分を待ち受けてはいる筈はないと思っているのだ。でもそんな運命がもし自分を捉えたら、という想像には心楽しくなれるのである。人間はそんな風にして生きているものだ。あらかたの人間は、傲慢にも卑屈にもならず、静かに、何かを待ちながら生きて行く。
★(舞台) 「今日われ生きてあり」 神坂次郎原作
戦後60年特別企画 前進座公演
死に赴く、知覧の特攻隊員の出撃をテーマにした反戦を訴える作品である。終戦記念日に20数万の遺族が靖国神社を参拝し、総理大臣の公的参拝が国際的にも取り沙汰されている今日、こうした作品が取り上げられるのにも意味があるかもしれない。
知覧の三角兵舎跡の記念碑で始まり、同じ場所で石碑にビールをかけながら「青春が美しいなんて言わせないぞ」という、作者(志村智雄演ずる)が厳しい表情で言ってのける場面で幕が降りる。劇中、次々とエピソードが描かれるが、その取材に当たった原作者が姿を見せて感慨を洩らす。早朝、特攻隊員の死地に赴く出撃の場面や、軍指定の食堂で大らかで優しく包んでくれる女主人を母のように慕う隊員たちの言動が描かれる。志願で入隊したものばかりだから、自ら自爆機となって死んで行く事を至上とする若者ばかりである。ある場面だけを見ていると、軍国主義の美化のようにも映る。勿論作者の意図は反戦である。しかし、その描き方は今までのものとは異質なものを感じる。聞くところによると靖国神社との繋がりの強い観客も動員されているとも聞いた。
帰途についた僕は、今日の舞台と、「聞けわだつみの声」や「ひめゆりの塔」との位相の違いが気になっていた。戦後、市民としての戦争受難の物語が主流を占め、まさに軍国主義に染まり、自らをその中に位置付けて死んで言った「プロ」の若き軍人の視点からの作品が欠落していた、いやむしろ避けて通ろうとしてきたのではなかろうか。そんな不安と不気味さをそこはかとなく感じ始めたのである。僕の少年時代、妙義の集団疎開地で声を上げて泣き、畳を掻き毟って迎えた敗戦。あの時の僕の心情がこの若き兵士達にダブって来るのは何故なのか。当然そのイメージに危険と不安を感じながらなのである。この欠落部分が、日本人の内部に、過去の侵略戦争否定と人間の生命の尊厳とをしっかりと結び付けて反戦志向を定着しきれずに来た原因なのではなかろうか。「犬死にされてたまるか」という気持には、反戦感情もあれば、その揺れ返しだって考えられる。靖国の「亡霊」が、いまだに吹っ切れない現状と合わせて、この芝居を考えてみる必要があるように思う。アジアの中の日本をいう視点を確かなものにして行くためにも、必要な作業ではなかろうか。
(2005・8・19記)
★ (舞台ーミュージカル)「広い宇宙の中で」劇団スイセイ・ミュージカル公演
博品館劇場にて
プログラムは、カラー写真が豊富で上等な作り、音楽CD付きで、「Ⅰ幕が終わってから封を切ってください」とアナウンスが入るほどの慎重さ。お金を掛けてるな、力入ってるなと頷ける。
いざ幕が開くと、出演者の勢いは並みではないと感じるほどの張り切りよう。しかし僕の音痴のせいか、ハーモニーを美しく感じないのだ。皆の声がぶつかり合っていて軋みを感じる。何故だと思いながら、舞台を見守る。ニューハーフの世界が出て来たり、新しい価値観で人間の行動や好みを考えなおそうとする努力は良くわかるのだが、それが由緒ある、お金持ちらしい御邸での出来事であり、新しい家族関係へ進もうとするドラマらしいと気付き始めた。でも一向にそのリアリティが伝わってこないのだ。何故だろう、とまた考え始めた。やはりストーリーの必然性とか、リアリティは作品にとって命だと思うのだ。これは小説でも、芝居でも何でもそうだが、どんなに素晴らしい音が流れていようと、この基本が出来てないと、感銘を与えることは無理だ。
実は僕はミュージカルが苦手で、こんなことをとやかく言う資格もないのだが人一倍感受性は強いと思っているし、音や声の美しさについても一応の聞き分けは出来るとも思っている。鑑賞会でも、時折聞いているのが辛くなるほどの作品に出あうこともある。でもこの作品はそれほど下手でも、熱意が感じられなくもない。元気いっぱいの公演である。何が問題なのか。
「広い世界」とか「夢」といった人間が生きて行くために極めて大切な要素が、ミュージカルでは、安易に「歌」となって「音楽」となって、出て来ることが比較的多いように思う。しかし、「広い」は「狭い」という現実、「夢」は「厳しい現実」に対応出来るくらいのリアリティがないと、「広い」も「夢」も色褪せて、偽物になってしまう。後半になって、住み込んで悪事を働こうとした姉弟の姉が、自らの過去を曝け出すようになって、少しずつ見応えが出て来た。歌にも演技にも僕の神経は正常に反応した。部分的な評価になるが、この部分の「良さ」がどこにあるかを再検討して、全体を仕上げ直して欲しいような気持である。音楽的要素が夢の質を誤魔化す様だと、これは悪夢になってしまう。(2005・7・8記)
★ (舞台)「家族の写真」作:ナジェージダ・プトウーシキナ 訳:大森雅子
演出:鵜山 仁
出演:中村たつ・高田聖子・石田圭祐・川口 桂
観終って呟いたのは、「ロシアでもこんなお芝居が作られるようになったんだ。」ということだ。学生時代に叩き込まれた「社会主義リアリズム」からすると、こんな「ふざけた」ストーリーは出現しなかっただろう。吐いた嘘がどんどん大きくなって現実の生活を実際に変えて行ってしまう話である。母はもう老齢で、いつ死ぬかわからない状態。傍で介護する女性は、結婚もせずに40台になってしまった娘。母はこの娘が結婚もせず、孫の顔も見ず死んで行くことをこよなく不幸だと思っている。「恋愛した事があるのか」という母の質問に適当な嘘をついて、逃げているが、見知らぬ男が間違えて訪問して来たり、得体の知れないギャルが飛び込んで来て、これまた即席の隠し子に仕立てられ、居もしない家族が、だんだんに出来あがって行く。それがその場に居る人間たちの心の痛みを癒して行く。そこには始めから顔の揃っている家族よりも大きな幸せが膨らんで行くのであった。
多少無理のあるストーリーなのだが、やり方ではもっと自然な流れができるのではないか。感じたことを書きとめて見よう。
1)廻り舞台を頻繁に使って、観客の視点を移してゆくのは良いとして、それに合わせた役者の動きがどうもギクシャク感じられる。役者の動線の工夫が必要なのではないか。
2)軽快なリズムで流れるセリフを殺すような、前半の舞台照明の暗さはいかがなものか。家具も壁も重厚な感じだけに、ストーリーの進行とチグハグな感じがした。明るくなった後半にはその印象は薄れるが。
3)娘役の女性は、母と擬似夫と孫を相手に演技をする訳だが、どうも動きが巧くない。役者の実際の年齢は知らないが、役の年齢と意識の認識が、ややずれているのではなかろうか。
4)欧米の喜劇の影響をかなり受けているのではないかと想像するが、所々にロシア的「構え」が垣間見えてくる。これは原作の問題なのか、演出上の問題なのか。
すべて終わっての帰り路、何かが胸に引っ掛かっていた。(2005・6・14記)
★ (舞台)「朝の時間」 作:水谷龍二 演出:永井寛孝
テアトルエコー128公演 出演:熊倉一雄 丸山裕子 安原義人 他
僕は何故か、テアトルエコーというと、拘りがあって観に行っている。彼らの喜劇が素晴らしいからではなく、「喜劇に拘る」「笑いに執着する」姿勢に興味を持っているからだ。翻訳もののコメディばかりやっていた頃、汗みどろで観客を笑わそうとすればするほど、僕らは固くなってしまうのは何故だろうとずっと考えていた。最近は日本の作家のものを取り上げて、相変わらず「笑い」に執着している。そして今回の水谷との出会いである。水谷龍二といえば、テレビ作家として、「コント55号のなんでそうなるの!?」などのお笑いを手掛け、今ではドラマの脚本、芝居の作・演出も始めている。94年には、ラサール石井や小宮孝泰らと「星屑の会」を結成している。うちの会でも「缶詰」を上演して、好評だった。
今回の「朝の時間」のチラシに載っていた文章を載せよう。
「73歳になった野崎昇平は、目も悪くなったし、そろそろ個人タクシーを廃業しようと考えている。東京郊外の都営団地で妻の君枝と二人暮らし。昇平の目下の楽しみはパソコン。昇平・君枝夫婦には三人の子供がいた。長男は中学の教師、長女は脇役女優、次男は失業中。めったに顔を見せない三人の子供たちが、次々と悩みを抱えてやってくる。久々に子供と迎える朝、淡々とすぎていく時間の中で、子供たちの嘆きが癒されていく。そして迎える老夫婦だけの朝・・・。五月のある一週間を朝だけで描いていく家庭劇。」
セリフも洒落ていて、充分に笑わせる。水谷のセリフは、どこか乾いた所があって、小気味良く笑える。熊倉と丸山の演ずる老夫婦が実にうまい。特に丸山には「歳を取るとあんな女房が良いな」と思わせるような女を感じる。熱演、好演である。熊倉との相性も良く、彼の飄々とした個性とピッタリだ。拘りなく接し、言いたいことを言っても結局いつか心を癒され、こちらも女房を思い遣っているような心の分かり合いが羨ましくなる。子供たちのとんでもない相談事も、それぞれの内部で折り合いがついて行くのも、母親の人柄故だ。
日本人の笑いが何か、をエコーは掴んできていると思う。注目し続けよう。結局は面倒な感情翻訳に悩ませられる洋もの喜劇よりも、「缶詰」「アパッチ砦・・・」そしてこの「朝の時間」のような、時代柄「乾いて」はいても、融けて行くような「笑い」に、快さを感じている僕である。(2005・6・2観、6・3記)
★ (舞台)「あゝ東京行進曲」原作:結城亮一 脚本:藤田 傳
演出:関矢幸雄 出演:はちまる総出演
2005・5・24,25の「たそがれ」に生々しい感想を書いたが、ここにも少し触れておきたい。歌手個人が主体的に生きたいという心を堅持し、大衆からも受け入れられ、一定の評価が定まって行く。これは「歌いたい」という主人公の情熱と、「自分も歌いたい」という大衆の情熱の出逢いである筈だ。しかし同時にその繋ぎ目に居る企業とか、国家の力も影響することも多く、時代によっては、これに大きく左右される。流行歌も軍歌も例外ではない。「歌わされる」現実も常に存在している。生きるエネルギーが吸収され、政治や利潤に利用される。歌う事も踊ることや書くことと同様、生きているものの「表現」なのだ。この作品の寂しい死を迎える主人公、佐藤千夜子は一旦は「新民謡」のヒロインとなって、大衆に愛されるが、さらなる「歌うことへの情熱」で、イタリアへとオペラの勉強に出かけて行くが、その間に日本の社会情勢は大きく動き、軍国日本に変貌して行く。大衆は軍歌の歌声にまみれている。敗戦。そして「リンゴの歌」とともに復興が始まる。千夜子の母の声であろうか、「人は人の中でしか生きられない」という言葉が、彼女の心の中で常に木霊している。名声を棄ててイタリアに旅立った彼女の心意気には、現状に甘んじてはいられない、自らを突き動かすものがあったに違いない。「人は人の中で鈍化する」という裏面もある命題を、彼女の素直な声質と同じように、素直に表現した生き方であったのかもしれない。かって自分が身に着けていた毛皮のコートを店先に見付け、着てみるが、店員の誤解から窃盗と間違えられるような惨めな生活に落ち込み、やがて行き倒れのように死んで行く彼女は、死に行く道々で、歌を口ずさんでいたのではなかろうか。
「1980」の舞台では、大仰な装置は何も使わない。数多くの黒い箱をマジシャンのように操り、どんな場面も作り出してしまう。黒い衣装だけを身に纏い、肉体と肉声のみを使って、どんな役にも早替わり、時には存在そのものも無にしてしまうのである。「黒」は自在性を演出する最適な衣装となっている。白く輝く1本の紐が、「月山」の背景を作り出し、日の丸の輪郭にもなり、教会にもなり、十字架にもなり、鉄道線路にも、汽車にもその姿を変える。ユニークな表現様式を創り出しているのだ。観客は、大笑いをしながら、「こんな芝居があったのか」と呆気に取られているうちに、帝国劇場では、見付けることの出来ない「演劇の世界」に招待されるのである。(「ねりま演劇を観る会」例会・2005・5・24,25を終わって、5・26記)
★ 〈映画)「阿修羅城の瞳] 監督:滝田洋二郎
出演:市川染五郎、宮沢りえ、樋口可南子
内藤剛志 等
歌舞伎的演出、時代アクション、鬼・阿修羅世界ラブストーリーであり、「陰陽師」顔負けSFXを駆使した、「コリャなんじゃ」的色彩濃厚作品である。評判になった舞台を今度は映画化したもの。監督は「壬生義士傳」と同じ監督。
率直言って、出だしやたらと激しいカットが断続的にヒョコヒョコと並んでいて、ストーリーがまるで掴めて来ないため、何度も居眠りをした。絵の色彩が歌舞伎、チャンバラが歌舞伎調、リアリティは切った時の出血と刃の血糊ばかり。「壬生義士傳」と同じ監督とは、とても思えなかった。
戯作者がはっきりと出てきた頃になって、文化文政の江戸が舞台で、染五郎の役が鬼殺しの達人で今は役者をやっている。もう一人偉く強く、りえ演ずる「つばき」を染五郎と取りっこする男が登場。ヒロインは尼風の女泥棒で、恋をすると鬼になり阿修羅に変わってしまう。染五郎とりえは出会った時から体にボタンの痣が出来てしまう程の惚れ込み様。りえは必然的にどんどん阿修羅へと近付いて行く。染五郎のチャンバラは並み居る鬼ども、それとりえを奪い合う男との激闘、そして何よりも凄いのが、りえ自身との切り合い、刺し合い、掴み合いである。これは明かに性的絡みであり、相手を殺さないと自分も鬼になってしまう、自分が死ねば相手も死ぬという、まさに目くるめく性交渉の乱舞なのだ。セリフにも「お前の体に突き立ててやる」とか「今度こそは最後まで来させておくれ」とか「とことん行かせてやろう」「お前の血を飲んで、私の血の騒ぎを宥めたい」と言った、極めて性的な暗示で満ち満ちている。戯作者の流麗な筆が草子の上を流れ、「俺はこの目で見たものしか書けないのだ」とのたまったりする頃になってやっと筋としての流れが見えて来るが、結局この作品と言うのは、何だったのだろうか。こんな事がやれたら凄いぞという作者や監督の悪趣味を一生懸命ワンカット、ワンカットに注ぎ込んで終わってしまったのではないか。りえの裸もあの辺でギリギリなのだということもお客は良く分かっている。それでもファンは気が気でなかっただろう。幻想的な場面を実験的に試みただけなら、お客を愚弄している。そんな競走はいくらやって見た所で所詮洋画には適わないのだ。(2005・4・21記)
★ (映画)「ローレライ」 監督:樋口真嗣、主演:役所公司他
原作:福井晴敏
戦争映画である。戦争の中で人間が選択する生き方、死に方がテーマになっている。ただ軍国主義・完全な国家主義の支配する戦争の中で、研究室で行われた実験のような、これは一味違った「戦争」である。設定は太平洋戦争終息直前の1945年8月始め。秘密兵器「ローレライ」を搭載した潜水艦「伊507号」が、広島、長崎についで、3度目の原爆投下計画である東京殲滅を食い止め、その後、姿を消す、という話である。アメリカの特殊撮影やCG技術と比べればチャチなのかもしれない、韓国映画の戦争描写の残酷なまでのリアリティから言えば、甘いという批判もある。しかしこの映画には、娯楽性だけでなく、戦後日本人が棄てて来た「国家と個人の死との問題」の再提起の意味もあるのではないか。戦後、国家主義を批判して、国のために死ぬと言うことを一笑にふして来た日本人に、実際に戦争の中にあれば、それだけでは済まされないという警告も含まれているのではないか。アジアの中で国際的な軋轢が高まり、防衛熱が煽られる中、安易な姿勢でこの映画を受けとめれば、安っぽい愛国心の高揚に結びついてしまう。ここには同胞のためにする自己犠牲が語られているからだ。東京を抹殺してしまう架空の原爆投下を想定して、絹見少佐以下の生き残り兵士たちは、伊507号に乗り組む。この潜水艦はドイツから手に入れた秘密兵器で、ここには「ローレライ」と呼ばれる特殊敵艦探知システムを装備した小艇を搭載している。このシステムは良くは分からないが、人間の感知力を科学的に改造して、イルカのような鋭敏さを持たせて、それを艇の操作装置に直結させ、まるで素潜りのように敵艦に近付き、正確に魚雷を命中させ沈没させ、音もなく静かに、いや、ローレライの歌を聞かせながら、立ち去って行くという、太平洋艦隊内で噂された秘密兵器であり、破壊せず捕獲拿捕せよの命令まで出ていたのだ。画面でやがて分かってくるのだが、このシステム用に開発された人間と言うのは、日系ドイツ人である美少女パウラ(香椎由宇)なのである。この辺の荒唐無稽さが「滑稽」だという批評もある。艦長の絹見少佐は軍人ではあるが人間的な資質の持ち主で、最後にテニヤン基地に突入する時も事前に、死にたくない者をボートで船外に逃がしてやる。東京の原爆投下を阻止するには命も捧げるという人間だけが、テニヤンに向かう。兵器として道具にされていた少女パウラまでが同意するのである。
チャチであろうが、甘かろうが、眠気も覚めて、スクリーンに吸い寄せられていた僕にとっては、少なくとも面白い映画であった。身近な人間の危機に際して、命を投げ出して救援しようとする「人間性」は強要されてはならないだろうが、決して、僕らから永遠に失われてしまったものではないと信じたい。「身近な人間」が「同胞」と言うことになり、非道な力で抑圧されている時には、抵抗を試みる事に人間の姿を見出そうとする側に僕も立ちたいと思う。国家と国民の関係のあり様をしっかりと分析して、自分の意思としての行為にしなければならないし、愚かに権力の手玉に乗ってはならないのは言うまでもない。(2005・4・21記)
★ (舞台)バレー「SWAN LAKE 白鳥の湖」 (オーチャドホール)
演出・振付:マシュー・ボーン 出演:ニューアドベンチャーズ
主演:ジェイソン・パイパー、クリストファー・マーニー
一口で言って、白鳥を男たちが演じる「白鳥の湖」だ。コミックな「おかまの白鳥」というのも来た事があったが、これは極めて芸術的な労作であり、モダーンバレーの冒険的トライアルである。白鳥が男なのだから、王子様との関係も恋ではなくて友情もしくはややホモがかった男同士の愛情と言って良かろう。踊りが下手で王室内の貴族的人間関係に疎外されていた王子は死を決意して湖に赴くが、そこで白鳥に救われ、踊りの妙技を授けられて、貴族達の中に戻って行くが、浅はかな妬みや恨みの世界は、王子を受け入れる事は出来ず、人間を愛した白鳥も仲間達から疎外されて、二人は存在を認められない。夢のような二人の愛情の結び付きは幻想的な演出で見事に表現される。聞きなれた曲、見慣れた白鳥たちのさまざまな踊りの姿も、男になって、その華麗さ、繊細さは、舞台一杯に構成されたダイナミズムや劇的な力強さに一変する。「ウエストサイド物語」や「キャッツ」を観た時の驚きと新鮮さがここにもあった。(2005・4・16観/21日記)
★ (舞台)「しのだづま考」 作・ふじた あさや
出演・中西 和久
中西和久の一人芝居である。ホーム・ステージを改修のために使えなくなったねりま演劇を観る会の3月例会である。小ホールのため3ステージの公演となった。
実は知名度から言っても、内容の地味さから言っても、これほどの好評を得るとも思っていなかったし、僕自身がこれほどステージに釘付にされてしまうとも思っていなかった。それほどの感銘の出来栄えであった。こういう芝居があったんだ、という新しいジャンルに眼を見張る思いであった。いわゆる現代劇の流れの中で色褪せてきていた日本の「芸能」の世界に、逆に居直る事によって、見事に現代性をリアルに甦らせたと言って良いだろう。
「狩で追われた狐を助けたために命を狙われることになった安倍保名(あべのやすな)は、森でさまよううちに、葛の葉と名乗る美しい娘に助けられる。やがて二人は恋に落ち、子供を授かって幸せな生活を営むようになった。しかしこの葛の葉こそ、保名に助けられた狐の化身だったのである。ある日、庭の蘭菊に見惚れていた葛の葉は、つい人間に化けていることを忘れて、真の姿をわが子童子丸に見られてしまう。もはや隠し通せぬと悟った葛の葉は、そばの障子に『恋しくば たずね来て見よ 和泉なる 信太の森の うらみ葛の葉』の一首を書き残し、泣く泣く元の棲家へと帰って行く。数年後、保名は成長したわが子清明(童子丸)と都に上る。葛の葉から授かった超能力で帝の病を治した清明は、数々の奇蹟を起こし、天文博士と召され、その栄華・栄光は末代まで栄える。」というのが荒筋だが、この物語を中西は一人で演じ、中で自分の解説や解釈をも語りとして付け加え、太鼓、三味線なども演奏し、巧みな語りの技法は、師の小沢昭一にも引けを取らない。見事な日本的「間」を駆使して、息も吐かせぬ緊張感で1時間45分を構成している。
歌舞伎だと眠ってしまう、浄瑠璃だと言葉が良く分からない、というお年寄り、若者などにも食いつきの良い作品となっている。「山椒大夫考」「をぐり考」とともに、この説経節の一人芝居は「3部作」として今後も大いに期待できる舞台である。
★ (舞台)「片づけたい女たち」 作・演出 永井愛
出演・松金よね子、岡本麗、田岡美也子
3人の女優がグループる・ばるという演劇活動を続けている。1回限りではなく、今後も継続して公演をして行くという。永井愛さんが持ち前を発揮して女性の生活と心理を笑いと生活悲哀とで彩って行く。それにしてもこの3人にはぴったりの芝居である。
緞帳が上がると客席はどよめく。舞台には普通のマンションの一室が現れ、足の踏み場所もないほどのゴミ(と言ってもすべて生活用品なのだが)が溢れている。これはツンコ(岡本)の居室である。このゴミの山に観客は動揺するのだ。「何だ、これは!」という気持だろう。ここにバツミ(田岡)とオチョビ(松金)という二人の親友が訪ねてくる。最近連絡を取れなくなったツンコを案じて、二人はツンコのマンションを探し当て、訪ねて来たのだった。二人も先ずはこの部屋の凄まじい状況に目を見張るが、やがて手伝うから部屋を綺麗にして、近くの焼き鳥屋で新年会でもやろうということになり、嫌がるツンコを説得して、近況報告や昔話などに花を咲かせながら、片づけ始まる。「片づけ」の考えも方法論も異なる3人の共同作業はなかなか捗らない。むしろ3人のお喋りの中で3人の関係、一人一人のこれまでの人生の流れ、現在の生活環境、などがそれとなく分かってくる。それも観客一人一人の想像力の中で広がって行き、3人のキャラクターの姿が見え始める。ツンコには同棲していたらしいシローさんという30台の男性がいて、最近の生活振りに業を煮やしたツンコが怒鳴って追い出してしまったらしい。所がこれから予定している新年会の場所である焼き鳥屋にまた舞い戻っているという。オチョビは飲食店らしいお店をやっているが、最近店を手伝い始めた嫁のやることなす事にいらついている。裏には充分愛情もちらついているのだが。気性が激しく苦労して来たバツミは、勝手な事を言って感情的になるツンコと対立して、泣いたり喚いたり、帰り掛けたりするが、いつもオチョビに宥められては、また良いムードが戻ってくる。あるきっかけで遅れ馳せながらの課長への昇進を黙っていたことを二人に責められるが、それをきっかけに昔あった人間関係なども絡んで、大事な局面で自らを欺いて見過ごしてしまうことは最大の罪だと自己を責めるツンコ、そこまで考えなくとも・・・と宥める二人。そんなこんなで、笑いとしんみりとした静寂をちりばめながら、舞台は進行して行く。年齢50台に入り、社会的にはいろいろな惨めさの中で相当な経験もし、男なんてと言う気持にもなり、子供の嫁との関係で悩むなど様々な状況の中でまだまだ続いて行く筈の人生の意味を考えながら懸命に生きて行く。もっと身の回りを片づけたいのだが、なかなか片づけられない、下手をすればそのゴミの山に埋もれてしまう。その比喩的な意味も深いものがある。そんな心情が良く伝わって来る。終わりの方で出てくる「私、もう心のパンツを脱いでしまった気持なのよ。」というセリフは、彼女たちの心の絆を思わせて感動的である。3人の熱演には心からの拍手を送りたい。(2005・1・29記)
★(テレビ)「デビル」アラン・パクラ監督、主演:ハリソンフォード
ブラッド・ピット
テレビを観始めて、昔ハリソン・フォードのファンだった同僚と映画館で観た映画である事に気付いた。IRAがアイルランドの内戦で武装闘争を繰広げていた頃の映画だ。アメリカもここまでの映画は創れるのか、この辺が限界なのだろう、などと思いながら、今のイラク問題、テロ問題と同様の重いものを背負って劇場を出て来たのを記憶している。
新聞には、「警察官の住む家に国際テロリストが下宿する」と短い解説が付いている。この表現に9・11以後の反テロキャンペーンの時代にいる事を痛感する。アイルランドの反政府武装グループが弾圧され、あちこちに逃げ惑いながらも抵抗を続け、アイルランド系のアメリカ人のシンパなどをつてに、武器調達などを行っていた。この警察官の心情は、この新聞の解説を書いた記者よりももっとIRAの心情を理解していたに違いない。恐らく9・11を経験した今のアメリカでは、この映画は作れないのではないか。
我々は簡単に暴力は無条件で間違っている、平和こそが大切なのだ、と誰もが思い、誰もが言う。しかし現に抑圧された生活を送り、政治的自由を認められず、圧倒的に威力のある武力で、「見たら殺せ」式に扱われている人間にして見れば、そんな抽象的な理想は、霞みのような物に過ぎない。しかし、この映画では、IRAを支持する側の女性の口から、闘争グループの行動隊長になっているブラピに「闘争しながら、罪の意識にかられることはないの」と聞かれ、はっきりと「時にはあるさ。でもこちらから止める訳にはいかない」と応えている。警官のハリソンフォードも「無闇に撃ち殺していい人間はいない。逮捕が原則だ」と言い張っている。ブラピもこの警官に「あなたは良い人だ」といって、涙を流しながら、彼の手から逃れようとする。武器を積んで国に逃れようとする船の中で、ブラピとハリソン・フォードは銃撃戦となり、相撃ちの末ブラピは死に、重傷のハリソン・フォードが沈鬱な表情で船の操舵輪を操り、港へと戻って行く。「誰もその立場にならないと本当の正しさも何も分からないのだ」というブラピの言葉には、まだ希望が持てたのかも知れなかったが、現在は、その言葉には絶望的な響きがある。「殺し合いは必然なのだ」と。
★(映画)「北の零年」 定行 勲監督、主演:吉永小百合、渡辺謙
前から観ようと期待していた作品だが、やっといつものユーナイテッド・シネマ入間へと足を運んだ。平日でもあるし、いくら小百合が出るにしてもと、高を括っていたのだが、一寸油断しているうちに長い行列が出来ていた。週末の「ターミナル」とどっこいの人気だ。
たっぷり3時間かかる超大作である。僕は特にいわゆる「サユリスト」ではなかったのだが、彼女の魅力にはあらためてシャッポを脱いだ。清楚な中に芯の強い生活力を潜めた素晴らしい日本女性を立派に演じている。時代は変わってもあの強さが日本の女の強さなのだと納得した。廃藩置県が敷かれ、領主から国家の新政府へと権力が変わって行く過程で、領民達の戸惑いと生活不安、そして棄民を経験して、精神的な支えを失い、苦しい生き方を強いられる淡路島の藩出身の元武士達。
藩主への忠誠を支えに、見た事もない北海道の新天地で、「新しい国作り」を夢見て、開墾と領主のお屋敷作りに汗を流しているが、後から到着する筈だった移民の船が難破したり、米作りも気候の違いも祟って、なかなか成果が上がらず、豊かな広大な畑の夢も遅々として進まない。やっとやってきた領主の若殿様は、時代の趨勢には勝てなかったと、廃藩置県の令の実施を告げ、そそくさと引き上げてしまう。大木を苦難の中で切り倒し、建造した領主の屋敷の前で、茫然と立ち尽くし涙にくれ、やがて狂喜のように自らの髷を切り落とす指導者たちであった。「俺達は捨てられたのだ」と叫びながら。その場面を見ていて、ニュアンスには違いがあるが、終戦直後、宮城前に集まった国民がひれ伏して泣き叫び、時には割腹する旧軍人も居た。生きる支え、精神構造の中枢を失ってしまった人間の姿だ。それがいかに古い時代のものとは言え、神国日本の天皇の存在を軸にして、集団疎開の飢えを耐えて来た僕には、彼らの悲惨な悲しみは素直に伝わった。
藩に捨てられ、国に捨てられた彼らは、初めて自分のために生きるという本当のスタートに立たされたのだった。国に裏切られた人間達は、今度は仲間達の中での裏切りに苦しむ事になる。飢えの中では、妻が夫を、夫が妻を、仲間が仲間を裏切らなければ生きられない極限を強いられる事になる。「赤い月」のヒロインは、その裏切りをむしろ開き直って、自己肯定して行く傾向があるが、ここでは個人の生だけの問題ではなく、旧藩主の傘下で結び合った宿命に束ねられた辛い辛い「集団」としての人間達なのだ。一緒に生きるということだけが、人間であることを認め合える唯一の喜びなのだった。しかし生きるということが生易しいことではないということが、身を切るような不信行為へと追い詰められ、心荒む思いによって立証されて行くのだった。農地としての成功がなかなか進まない中、砂嵐のようなイナゴの大群に襲われ、僅かな希望も毟り取られてしまう。
吉永演ずるヒロインは、夫(渡辺)の宿命的な歩みの仕打ちに耐えながら、先住民や外国の移民との繋がりも出来、馬の飼育を始め、素朴な牧場の運営に着手する。農耕馬の利用で開墾の効率も向上して来た。娘も賢く、美しく、逞しく成長していた。新政府は、徴兵義務を免除する代わりに、馬を軍馬として徴用すると要求して来た。その命令を文書を携えて執行しにきた高級役人こそ、吉永の夫(渡辺)だったのである。母娘の強硬な志は、廻りの仲間達を、共有していた「夢」に再び団結させる事になる。一度は権力に傾いたもの、夫婦で離反していたもの、五稜郭の戦闘に破れて、逃亡していた男も、すべてが銃で武装した兵士達の列に、毅然として、鍬を手にし、立ち向かうのであった。突如放馬された馬の群れに、止む無く撤兵して行った牧場には、やがて原住民(アイヌ)にリードされた馬たちの群れが、蹄の音も高々と戻って来るのだった。北海道の厳しいが美しい自然。逞しい馬たちの走り。歴史の中に呑み込まれていった人間達の生の闘いは僕に大きな感動と衝撃を与えた。
「セカチュウ」という言葉まで生んだ映画「世界の中心で愛を叫ぶ」を創り上げた定行監督の瑞々しい才気に、心から経緯を捧げたい。
★(映画)「ターミナル」 スピルバーグ監督、トム・ハンクス主演
僕は特にスピルバーグのファンではない。名監督だという評価にもかかわらず、「ジョーズ」「ET」「インディ・ジョーンズ」「フック」「未知との遭遇」位しか観ていない僕は、全部観ようと言うほどの吸引力がなかった監督だ。先入観としては、確かに映画にしか出来ないような表現を追及していることは知りつつも、空想的ロマンの映画の追求というイメージが強かった。
また、主演のトム・ハンクスという俳優の作品で心に残った作品は「フォレスト・ガンプ」位なのだ。そんな僕が「ターミナル」という映画を観たために、これからは、スピルバーグをもっと観よう、ハンクスの魅力をもっと追いたいという気持になった。
ハンクス演じる主人公は、ある日ニューヨークにある空港・ターミナルに到着する。ジャズの熱狂的ファンで、有名な演奏家のサインを直接本人から貰ってそれを収集していた父の意思を継いで、まだ揃っていないサックスの奏者のサインを貰いにニューヨークに到着した所だった。しかし運悪く、自国では革命が起き、政権が崩壊して、国交がストップしてしまったので、空港から出られなくなる。空港当局との話し合いで、当局側の言葉は理解できず、目配せに近い合図も読み取れず、上手く立ちまわれば、外に出られたにも関わらず、馬鹿正直に対応するために、9ヶ月も空港に滞在することになってしまう。その間、食べて行くために空港内で壁塗りなどの仕事について、空港内で働くいろんな仲間と近付きになり、その実直な人柄から、初めは呆れられながらも、次第に皆に愛され人気者になって行く。彼を庇おうとする仲間はいろんな災難に会うがそれでも彼は皆の注目する存在となって行く。手に持って離そうとはしない空き缶、にはジャズ演奏家達の生のサインが詰まっていたのだ。それが原因でスパイの嫌疑さえ掛けられるが、今は「出られない」、でも条件が揃えば「出られる」ことを信じてあらゆる困難に耐えて9ヶ月も待つ。遂に外に出る機会がやってくる。しかしそのために彼を愛する大切な仲間の命が奪われてしまう。それを見て一時は帰国を諦めようとするが、空港の仲間たちは、彼の夢を諦めるのは卑怯だと迫り、最後のジャズ演奏家のサインをもらう事を実現させ、祖国に帰る決意をさせる。
僕は笑い、涙し、はらはらしながらこの映画を堪能した。主人公を頑ななまでに実直な演技は、フォレスト・ガンプの主人公の記憶とダブルイメージして、あの時の感動も甦った。何かを「待って」生きる事の素晴らしさ。画面の中に生きているどの人間も何かを待ちながら、今日から明日へと生きて行く。実現を疎外する様々な障害も「待つ」力に押されてやがては道が出来て来る。この辺に昔からのスピルバーグにあるロマンチシズムは健在だが、あり得ない状況設定もリアリティに支えられたものとなっており、「待つ」という人間的な行為をその手段としているために、一層彼のヒューマニズムの前進を感じさせる。スピルバーグの技法、ハンクスのキャラクター、空港という多国籍領域の舞台この3つが見事に調和した名作だと言わざるを得ない。(2004・12.28記)
★(映画)「レディ・ジョーカー」高村薫原作 渡哲也主演
犯罪映画と銘打って宣伝。見始めて30分程は、どうなるものやとはらはらした。僕は最初から「おお、いいリズムで乗れるな」という映画が好きなので、この散文的な、親父の愚痴のようにぼそぼそと始まる乾いたタッチが、淡々と語るが如くが方針なのかもしれないが、これでは駄目だなと感じ始めていた。隣で女房はもう頭を垂れていた。映画のリズムは、小説のリズムとは違う。
兎に角期待していたので、居眠りもせずに付いて行ったら、少しずつ乗ってきたんだ。「社会派作品」という定評がある時には、もしかしたら分かり難いという警戒心が必要だ。前編乾き過ぎと言うくらいにリアルなのに、未だになくなったとは言えない社会的差別で落ち込んだ階層の人間が競馬場で偶然つるんで、「レディ・ジョーカー」なる一味?を作り、「日の出ビール」を相手取って20億円恐喝に及ぶのだ。会社の内部の矛盾(社長の弟の娘が部落出身の恋人と関係がある)を利用しての犯行。捜査の過程で会社が警察を裏切って行動するとか、警察内部の人間がこの競馬グループの一員であったりと、かなり不自然な(いや、あり得ないとは思わないのだが)設定が、出てくる人物の相互関係の中に「人間」を見付けることを困難にしている。完全犯罪にするために、会社に対する怨念の1点以外何の繋がりも感じさせないグループになっているのだ。永久に口を開かないであろう警察関係者のメンバー逮捕。保管場所の部屋にひっそりと置かれた20億円。金銭目当てで無い復讐の結果の風景のみが印象に残る。原作に興味が湧く。
僕としては、善意でこの作品の意図は認めるが、映画としての評価はゴメンナサイと言うしかない。動機にまで作為を感じるような作品は駄目だなと思うしかない。(04・12・13記)
☆比較的最近の「たそがれ」の記述から同じジャンルの感想をこの欄にコピーしてみた。今後の感想はもう少し緻密なものになるだろうと思うが、一先ずはご勘弁を。(04・12・11記)
★(映画)ユナイテッドシネマ入間で、宮崎さんのアニメ「ハウルの動く城」を見た。「千と千尋」を超える動員数と宣伝されていたので、期待していたが、もう「千と千尋」を最後にすると言っていた監督が敢えて製作した割にはストーリー性、総合性から言って、僕には前作を超えてはいないと思った。「もう一つ」という監督の思い入れは、確かに感じられるそのイメージの斬新さ、絵の美しさ、幻想性、そしてお得意のスピーディな動きの素晴らしさはいうまでもないが、大切なストーリー性の点で、幻想的な魔法の世界の着想に掻き乱されている感がする。戦争を否定するテーマ性も現実感が薄れてしまっている。動員数の増加は「千と千尋」の評価の影響であろう。(04・12・4記)
★(舞台)「PIAF」 栗原小巻さんの舞台にはすっかり酔ってしまった。自己破壊的な人生を送り、シャンソンを自らの人生で歌ったピアフを、見事に演じていた。思えば彼女の役柄はこのような破滅的な女性の役が多く、あの温和な人となりが一変するのだ。下積みの生活から身に着けた卑猥で下品な言動をする女性を、素晴らしくリアルに表現できるのだ。むしろそうした女性への共感に根差した演技なのだろうが、女優としての小巻の芝居作りの根底には、日頃の自分を破壊する冒険が楽しくてならないという自虐性すら感じてしまう。連発される性的な言葉を武器のように使って、あそこまで自分のイメージをぶっ壊せる人と言うのも珍しいのではないだろうか。ピアフを中心とする芝居作りであるために仕方ないのだろうが、街娼上がりの彼女が世界一高いギャラを取るシャンソン歌手に成り上がり、歌一つの鬼となって、日常生活は凄まじく荒れたものとなって行くのだが、彼女を取り巻く人間達が、余りにも「惑星的」存在で、人間として平べったくなっているのが気になる。消耗品のように次々と変えられるナイト役の若きツバメたちの惨めったらしさは、演技不足も伴って、一層惨めになる。すべてが小巻の引きたて役である。昼は座席騒動で、観る気になれず、昨夜の飲み疲れも出て、ぼやーっと過ごす。夜の部にはいって、座席にもゆとりが出、Iさんの奥さんの座席をいただいて、前の方の席で、小巻さんの魅力を堪能した。「一味」の昼の部の参加者には、座席の面で申し訳なかったと思っている。疲れがどっと出て、終演後、飲む気力もなく、搬出も失礼して、9時半に帰宅。(04・12・2記)
★(映画)しばらく映画を見てないので、検索して見ると「隠し剣、鬼の爪」と「笑の大学」をやっていたので、行く事になった。珍しく和子も同じもので良いと同意した。二本見るには、帰りは9時頃になる。運動のつもりで、帰りは歩きになる。初めに「隠し剣・・・」を観る。山田洋次と藤沢周平の組み合せで「たそがれ清兵衛」と同じ。今回の方が画面は明るい。ストーリーの展開も明解で絵も綺麗だ。やや通俗なハッピーエンドのきらいはあるが、松たか子の幸福のためにはこれも良いだろう。剣法仲間だった友人が江戸に出て権力争いに撒き込まれ、謀反人の汚名を背負って、郷帰りしてくる。牢を破り村人を人質にとって立て篭もった友人を切るようにとの藩命で、戸田流の使い手を訪ね、実践用の極意を授けられる。既に戸田流では友人と共に1,2の使い手となっていた2人の対決なのだ。この藩の家老をはじめ腐敗が進んでいた状況の中で友人は彼の捨て身の剣によって切られるが、同時に隠れた狙撃者によって右手を吹き飛ばされ、撃ち殺された。斬った主人公の怒りは募る。彼は身分を捨てる事を決意して、最後の手段「隠し剣、鬼の爪」を用いて家老を摺れ違いざまに刺し殺す。ずっと心の中で想っていた使用人の女を愛を打ち明け、伴って蝦夷の地へと落ちて行く。どうにもならない権力構造の中での抵抗と反逆の悲劇だが、何故か僕の心は沈まなかった。「隠し剣」の故か。(04・11・29記)
★(映画)笑の大学。三谷幸喜の作品だが、観る会でも彼の作品の見事な言葉のマジックに酔わされたことがあるので期待していた。役所演ずる警視庁の検閲官と稲垣吾郎演ずる浅草の座付き喜劇作家の2人の対決でドラマは進んで行く。昭和15年頃の権力の統制の凄まじかった時代の話だ。権力とそれに一見屈して手直しを強要される作家との身を切り合うぶつかり合いなのだ。その中心は「笑い」なのだ。心から笑った事のない検閲官と笑いを作る事に命を賭けている作家との攻めぎ合いの中で、2人の内部が次第に微妙な揺れを見せ始め、攻めぎ合いはやがて交流となって、2人を結び付けて行く。当時そんな事が起こり得たかどうかが問題なのでは無い。「創る」という行為は権力の内部にまでやんわりと侵食して行ける可能性を三谷は信じているようだ。権力との闘いを政治的な行動だけに直結するのではなく、あくまでも人間の表現行為としての「笑い」を武器にした男の物語である。赤紙を受け取り徴兵されて行く作家に検閲官は「生きて戻って、また芝居を書け」と叫ぶのである。役所と稲垣の演技力は三谷の世界を描くのに充分な役割を果たしている。(04・11・29記)
★(舞台)六本木でテアトル・エコーの喜劇「ルーム・サービス」を観る。例によって翻訳もののコメディで、やはりいつも僕が言っている「笑わそうとすればするほど観客は笑わなくなる」壁が破れていない。訳と演出を担当の酒井洋子さんがプログラムに書かれているだけの成果は出てないように思う。劇場の近くのホテルに滞在する劇団一座が経営上のピンチで宿泊代他が払えず、常套の手練手管で誤魔化そうとする。ホテル側もそうはさせじと攻防戦が始まる。動きも大きく、決して演技も下手ではないが、観客席からは遠慮がちな反応だけ。日本人の笑いは、動きよりも言葉が大きな役割を占めていると思うのだが。この辺がいつもエコーさんが、徹底的に喜劇と取り組んでいる努力にはシャッポを脱ぐのだが、僕自身が翻訳喜劇の前で身を固く閉ざしてしまうのだ。(04・11・5記)
★(舞台)無名塾・「いのちぼうにふろう物語」。さて舞台だが、やはり大した物だなと思う。大物は仲代と山本だが、それは確かに光っている。しかし、若手がなかなかに大活躍。ただ、発声が悪いのか、歯切れが悪いのか、かなり良い席からも、聞き取れないセリフが多い。それが残念だったが、ダイナミックな舞台展開(人工廻り舞台の繰り返しは、やや視覚を苛立たせるが、大きな流れの中では許せる範囲だと思う。ならず者のような人間の集団が、一人の気弱な男の命がけの恋を成就させようと命を掛けた金作り。それも見事に権力のトリックに嵌まって、仲間は皆殺しに遭い、恋する男も自分に金を与え死んで行こうとする男を殺して金を奪おうとするような行為に及ぶが、過ちに気付いて、金を押しいただいて、好きな女の身請けへと走る。金を与えた山本圭が自殺したのかどうかは定かではないが、仲代を中心に「男の死に所」を悟った最後の権力への抵抗は歌舞伎まがいの大見得の舞台となる。暗い舞台を救ったのは、恐らくこの「負けの大見得」だったのではないか。悲劇的な負けにも負けにもそれなりの「華」があるものだ。(04・10・25記)
★映画評「誰も知らない」
この監督が僕等に、いや僕にかもしれない、突き付けているものは何なのか?一人の人間の生活をこれほど淡々と追い続けて、まるでルポの様に生活の襞を、時には物悲しく、時にはアンニュイに、時には激しい嬉しさや悲しみに、しかも一つ一つが「美しく」描かれている。美しくに括弧がついているのは、決して美しくない場面までが美しいからだ。画像的にもそうだが、空間を切り取る時に働く彼のポエジーがそうさせているように思う。
母親の道義などは問題にしたくない。多かれ少なかれ同じような「自分勝手」(明が母親に面と向かって言うたった1つの言葉だ)を僕達はやっている。自分勝手は何も彼女だけの専売特許ではない。その証拠に彼女はほんの端役だ。初めに顔を見せただけでまさに無責任に姿を消してしまう。監督も意識して無視しているのだ。
人間が生み出してきた人と人との胸が熱くなるような係わり、それが家族であろうと、仲間であろうと、親子であろうと、恋人であろうと、唯一人間が人間である存在価値のすべてが、どのようにしてどのようになくなって行くかを示している。それを淡々と涙を殺して描いている。監督が堪える分の涙が観客の目に溢れるのではなく、胸と腹に鉛色に沈んで行くのだ。
父親の皆違う子供を4人作った女。働き続け、不充分ではあっても仕送りを続けようとしている女。クリスマスには帰るよと言って姿を消した母親は帰らない。子供達は母親を半信半疑で待っている。この子達にサンタクロースはいない。次第に影が薄くなる母親への幻想の影がサンタクロースであるに過ぎない。監督は決してこの非常な女を責めない。
何故か。監督はこの母親のイメージをこの国のすべての母親に被せているのだ。父親ははるか霞んだ存在で、一人は、金をねだった主人公に1000円を与えて消えて行くだけ、もう一人は「お前は俺の子じゃねえよ。あのころはばっちりコンドーム着けてたからな」と言い捨てて、薄笑いを浮かべて行ってしまう。帰らぬ母も懸命に稼いだお金を子供達に送ってくる。しかし明かにそれでは生きて行けない。一番年上の明はスーパーの売れ残りのお握りを裏口で恵んでもらい、いつも小銭を数えては、チビ達の求めに応じてカップラーメンを山ほど背負っては幸せ一杯の笑顔で凱旋してくるのだ。つまり日本は心を失って行くリレー競走を続けてきて、今や最悪の状況の中で、世代の危うい釣り橋を渡っているんだぞと警告を発しているに違いない。その危機感を明の背中と横顔が見事に表現している。これは「不安の時代」の象徴なのだ。
「親がなくとも子は育つ」という言葉があるが、この映画ではこの言葉も破綻する。そんな生易しいもではないよという訳だ。頻繁に起きる子供殺しのニュース。親が子供を殺して生きようとする時代になっているのだ。民主化された「個の世界」は、封建社会の『世界』よりも過酷なのだろうか。人同志の繋がり、人同士の愛がここまで荒れた事を監督は冷静に描き続ける。
少年明の目の輝きが素晴らしい。特に3人の異父兄弟を支えて何とか生きている時の彼は素晴らしい。個が強調されて家族の人間関係すら崩れつつある日本の現状で、年下の少年達を生かすべく、全知を働かせようとする少年は美しい。意を決したまなじりは凄みのある美しさだ。しかしやがて彼にも限界が来る。それは自分の個に気付き始めるからだ。彼だって声変わりがあり、遊びに憧れ、自由な時間が欲しい普通の少年なのだ。極端な貧しさの中でも、彼の生活感覚の中には、醜いもの、怪しげなものに対する警戒心がまだ生きている。女友達が少年の生活を見兼ねて、「援助交際」で得たお金を少年に渡そうとするが、彼はその金を叩き落す。彼女の気持に少年らしい好意を抱いていた少年は傷つきながら街を走り去って行く。彼女もまた不登校で町をぶらつくうちに、この奇妙な「子供の集団」に惹かれて、ますます汚くなって行く家に入り込むようになる寂しい娘なのだ。彼女の家族関係も全く描かれてはいない。
母親と明、これが法的に書類に載せられる人間、あとはトランクで運び込まれた3人。日常的には「遊びに来ている親戚の子供」となっている。生を受けた時から環境の中に自分のアイデンティフィケイションのない子供達。こんな過酷な状況が事実あったのだ。こんな子供達を作った男たち、それを許した女。誰もがそのまま生き続けている。しかし監督は子供達だけの生き様を克明に追う。花を愛で、空き地の貧しい土で満たしたラーメン容器に野の草花の種を撒き、芽の出るのを楽しみに水をやる。彼らの心には生きる夢がはっきりと芽生えているのだ。
しかし労働の権利すらない年頃の子供達が、生きて行くというのはそれ程甘くはない。スーパーのお握りの廃棄分を貰いうけ、カップラーメンの買いあさりを続けながら、母親からの送金を期待する。生活に責任のある明は、労働権を認められてはおらず、アルバイトを求めてどこへ行っても雇ってはもらえない。明少年は小学校6年から、中学へと進む年齢に成長して行くが、学校には行けない。下の子供達も当然学校とは無縁だ。かって公の機関が彼らに救いの手を差し伸べた時、ばらばらに住まざるを得ないと分かり、4人は救いを拒否して貧しい4人一緒の生活を選んだのだった。学校に行けない明少年にとって「学校」は憧れなのである。少年は他の子供達にとって「親」の役割を自らに課している。それゆえに彼は学校に行けないのだ。校庭の隅に佇み、中に居る生徒たちを羨ましそうに眺める少年。校庭の先生に声を掛けられ、野球のチームの仮メンバーにしてもらってプレイ出来たことは少年の胸にいつまでも焼き付いている。彼はボールを空に高々と投げ上げて、落ちてくるのをしっかりと受け止めて遊ぶのが大好きだ。下の子供に「いつかモノレールに乗って飛行場に行き、飛行機が飛ぶのを見せてやるよ」というのが口癖であった。それは彼の夢でもあったのだろう。
この小さな人間達には、破局までが静かにやって来た。踏み台にのって植木に水をやろうとした時に、誤って倒れた一番下の女の子が動かなくなってしまう。狼狽するが助けを呼ぶ術もない。籍のない、「存在」のない小さな命が消えた。友達となった不登校の少女と二人で、動かなくなった下の子をトランクに詰める。この「家」に移る時、人に見られず運び込めるようこの子が詰め込まれたあのトランクには、もう体が成長して入らなくなり、他の二人が詰め込まれて来た大きい方のトランクだった。二人でそのトランクを運び、モノレールに乗って空港の外れの空き地まで辿りつく。無言で地面を掘る二人。傍に置いてある無言のトランク。少しずつ穴は深くなり、でもトランクを入れて、その上に土を盛ると塚のように盛り上がった。死体を隠したのではなく、墓に葬ったのである。二人は塚に向かって手を合わせる。立ち尽くす二人。茫然と塚を見守りながら、いつまでも座り続ける二人。
そして、再び街の中に少年の背中が在った。凛々しい横顔が在った。冷たく忙しいだけの街の顔が在った。何度クリスマスを迎えたら、彼らの前に光が見えて来るのだろうか。
(2004・9・15記)) |