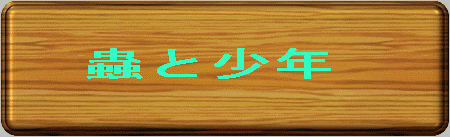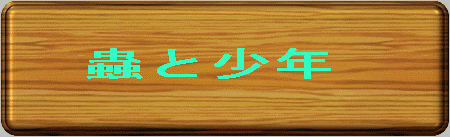|
蟲と少年
(一)
母が、庭の桜の木に毛虫が出るからと言いだして、池袋に近いA駅から徒歩数分の所にあった借家を捨て、転居することを父に進言したのは、ススム少年が五歳の時のことである。母が額に縦皺を寄せ、洗濯竿の支え木で払い落とした毛虫を火箸で摘み上げ、三重に重ねた新聞紙にくるみ、恐る恐る火を付けては焼き殺していたのを覚えている。その母の姿の周辺にぼんやりと家の庭が広がっている。ススム少年の危うげな記憶である。
父に連れられ、斜めに張られた「かしや」札を探し求めて、N駅の近くを歩き廻ったのは、それから間もなくのことである。
新しい住まいは、N駅から徒歩七、八分の所に位置していた。表通りから路地を少し奥に入った突き当たりの手前左手に、ごくありふれた木の門柱とガラス入り格子戸の木造平屋建ての家があった。門柱はかなり古く、白蟻に蝕まれた痕跡が明瞭であった。毛虫を嫌って移り住んだススムの母は、ここから発生する羽蟻に悩まされるとは思っても見なかった。南側の小縁の前に名ばかりの庭があり、東側には、幅六、七メーターで、奥の隣家との境の小路まで一杯に、この家には不似合いと言える程の庭が広がっていた。家の前の道の突き当たりは空き地になっており、中央に二本の高い青桐の木が立ち、周囲には青木やツツジなどの植え込みが土留めとなり、その向こうに一段と低く狭い畑が広がっている。その先は急に落ち込んでいて、広い畑が視野に飛び込んで来る。その畑の中央を左右に小径が走り、麦わら帽子の農夫や、行き来する一般市民の姿が見受けられた。後で判ったことだが、ススムの家の裏手を抜けて畦道沿いにその径に出ることが出来た。このあたりの畑は、少年の心象風景としては、いつも麦畑であるか、大根畑であった。
引っ越して来てすぐの印象は、極めて異様なものであった。ススム少年にとってそれは初めのうちある種の恐怖に近いものであった。南側の板塀の下は葉の透けた植え込みになっていたが、その植え込みに沿って、泥だらけの顔に、うどんのような鼻水を垂らした大小の子供らがずらり並んで瞳を凝らして中を窺っていたのだ。少年は思わず後ずさりをしたものの、顔の中には歯を見せて微笑みかける者もいて、敵意や恐れは次第に遠のいて行った。これは彼らなりの新入りに対する儀礼であったらしい。
A駅の近くにいた頃にも、兄達と付近の原っぱでチャンバラごっこに余念がなかった少年はさすがにその友達を一気に失い、全く異なる土地柄で、異様感に始まった新しい友人たちとの関係を友好的に進めるには時間がかかった。しばらくは独り遊びの時期が続いていた。しかしこの土地には、少年の好奇心をつなぎ止めるものが満ち溢れていた。都会に隣接する前の家とは違って、農村のただ中にあるこの土地では、動植物など自然との出会いには事欠かなかった。それはすべて少年にとってまさに驚異であった。
少年にとって、我が家の裏の畑に通ずる細道は、神秘の世界への秘密の入口であった。緩い坂になった細い畑道を小走りに走って、下の広い畑のただ中に出る。麦が植わっていて、採り入れの少し前には、少年の背を圧倒する位に茎が伸びていた。少年の手には粗末な昆虫網がしっかりと握られていた。風がやって来るのが穂先の動きで感じ取れる。思いっきり背伸びをして、穂の海の上を広く視界に取り入れようとする。麦畑の向こうに藁葺き屋根が見え、大きな欅の豊かな枝に抱かれている。
「来た!」
その方向に、少年の神経が矢のように収斂する。この時に傍に大人が居たとしても、恐らくその目に対象物を捕らえることは不可能であろう。近寄る気配の中にやがて像を結ぶのは、大型のヤンマがゆうゆうと飛ぶ姿である。ヤンマは大型のトンボで、黒い巨体に鮮やかな黄色い縞が描かれている。複眼の目はらんらんと輝き、逞しい黒い筋の入った透明な翅は、伸び伸びと広げられて、殆ど静止しているように見える。風に静かにそよぐ穂の上を、風に体を浮かせるようにして近づいて来る。少年の心には、今までに捕ったことのあるあらゆるトンボの姿が浮かび、あっと言う間に、この獲物が生涯の逸品であるとの判断が、重大な書類に決裁印が音をたてるようになされる。
とおすみトンボ、赤トンボ、しおからトンボ、麦藁トンボ、銀茶、など少年のレパートリーはかなり広い。すべて捕り方は異なるが、少年が嫌うのは、トンボの体を傷つけたり、汚したりする方法である。この土地の子供らは主にモチを塗り付けた細い竿を振るってトンボを粘りつける方法を用いた。しかし少年はこれを嫌った。羽がべったりと茶色のモチで汚れ、逃がしてやっても再び飛ぶことが出来ず死んでしまうからである。ベンジンで汚れを取ってから放してやったこともあるが、よたよたと飛んで、すぐ近くの草むらに落ちてしまった。少年は心が痛んだ。また大人の発想なのか、それとも意外に悪知恵の働く子供そのものの知恵なのか、小さな石や空気銃の鉛弾などを紐の両端につけて、投げて搦め捕る方法もある。トンボが餌と間違えて飛び掛かる途端に絡みつく仕掛けである。この方法ではトンボが汚れることはないが、紐がきつく絡みつくために、羽の筋が折れてしまい、やはり飛べなくなってしまうし、騙し打ちのようにも見えて、少年は一、二度で止めてしまった。やはり一番ためらいのないのは、網で枠の針金にぶつけないように素早く捕獲するか、そっと近づき自分の指で直接捕るかが、少年に定着した技術であった。
「来た、来た。」
少年は全身を神経の針にして、身をかがめた。麦の穂先の隙間から微かにヤンマの動きが見て取れた。昆虫網の竿を持つ手が汗ばんで来る。尾の黄色と黒の縞がはっきりと見える。麦畑の上を飛ぶ小さな虫を求めて飛翔するのであろうが、麦藁トンボや塩辛トンボのように穂先に止まることは滅多にない。穂先すれすれに飛び続けるだけである。少年はヤンマの動きから畦道の上を通る位置を想定して、身をかがめたまま小走りに素早く移動した。ヤンマの方は全く気づいている様子はなく、ゆっくりとその雄姿を誇示するように風に浮いて近づいて来る。
「捕れる。」
火花のような確信が頭をかすめる。頭上を通過する瞬間をとらえるのはもう目ではなく感だけである。一瞬白い昆虫網が麦穂の波の上に弧を描く。「かしゃつ」という軽い手応えがあり、少年は素早く伏せた網に手から先ににじり寄った。網の白い繊維がヤンマの翅の動きを伝えて震えている。左手でそっと網の上から翅を押さえ、右手を網の下に潜らせ指でヤンマの胴を軽く押さえた。時折激しく翅と尾を震わせ逃れようとする。翅を長く持っていると飛べなくなってしまうし、胴を押さえる指の感触も微妙である。弱くては逃げられてしまうし、強すぎてはトンボを傷めてしまう。少年はこのコツをすっかり体得していた。少年は捕らえたトンボの胴に微かな体温を感じ取っていた。胴の下の部分の動きでトンボが激しく喘ぎ、息づいているのがわかる。美しい複眼の模様に少年はしばし見とれていた。宝石のような輝きであった。それがクリ、クリと時折動いた。黒い尾を輪切りにするように見事な黄色が縞を作っている。(何故こんなに綺麗なのだろう。何故こんな形をしているのだろう。)少年は自然の生物に触れると、何時でもそう呟いた。理由の判らない驚異が少年の心に広がって行った。
この麦畑も早春にはまだ幼い麦の苗で緑の縞を作っているだけであった。農夫に踏まれる度に大きく逞しく育って来た。その時期には畦道の両脇に韮が植わっていて白い花を咲かせ、特有の匂いがあたりに流れた。韮の傍にしゃがみ込むと根元近くの黒土に黒い小さな穴が点々と空いている。始め少年はそれが生き物の棲息する穴であるとは思いも寄らなかった。何かの事で母親に叱られ、心の寄りどころに困って家を飛び出して来た時何気なくやっていた手なぐさみがこれを教えてくれたのだ。少年は柔らかく伸びた韮の新芽を意味も無く根元から折り取り、それを下の地面に空いているこの小さな穴に差し入れていた。韮の葉は三分の二ほど穴の中に潜り、残りを地面の上に残して立った。それが五、六本ほどになった時、初めに差して置いた方が、ひくひくと動いているのに気づいた。風かな、とも思ったが、それにしては動きが不自然であった。少年は何気なく韮の葉をつまみ上げて見た。すると今まで穴の中に入っていた葉の先端に小さな黒い虫が付いている。おでこのペタンコな妙な黒っぽい虫が韮の葉先に食いついているのであった。胴体は蛆のように伸び縮みして灰色から尾に行くにつれて白っぽく色が変わっていた。次々に、差し込んだ葉を抜いて見ると、その殆どに同じ虫が食いついているのだ。これは殆ど釣りの面白さに通ずるものがあった。勿論釣りのように技術を必要とはしないが、葉の揺れが一種の「アタリ」であり、僅かな重さではあっても、手応えを感じて引き上げる楽しさがあった。少年は、海岸で父に教えて貰った「まて貝捕り」を思い出していた。ブリキの板で砂地を斜めに切って行くと、輪郭のはっきりした穴が見つかり潮を吹いている。そこへ食塩を一つまみ投げ込むと、突然「まて貝」が角のように突き出して来る。そこを「待て」とばかりに掴むのである。貝は尻の肉を驚くほど膨らませて、抜かれまいと抵抗するが、所詮は引き抜かれてしまう。貝の方は潮が寄せて来たと感違いするらしい。捕るのは面白かったが、固くて不味い味だったのも覚えていた。今偶然発見した出来事もこれに負けない興味を少年に与えた。少年はこの「遊び」を「韮虫釣り」と名付けて、気分が滅入っているような時には時の経つのも忘れて耽っていたものである。しかし、ある時を契機に少年はこの遊びを止めてしまった。母親に自慰をしているのを見られ、激しく叱られて家をとびだした。屈辱にまみれ、半べそをかきながら西の空が赤く染まり、影が長く伸びる頃まで韮虫を釣り続けた時のことである。ふと気づいて見ると、自分の周辺の黒い土の上に韮虫の死骸が無数に散乱していたのである。この虫たちには、自分の巣穴に戻る能力がないことに、少年は初めて気づいたのだった。今までその事に気づかなかったのが不思議な位であった。少年は自分のしていることに恐ろしさを感じた。悲しい気持ちにもなった。夕陽を受けて黒みを増した畦道に韮虫の死骸の白い部分が点々と続いていた。少年は逃げるようにその場を立ち去った。
(二)
大人は消防自動車のサイレンで火事場に群がるが、少年達は蝉の鳴き声に畳を蹴って外へと飛びだす。ススム少年の家の近辺でもこの風景は夏の日常茶飯事であった。油蝉は翅音をたてて突然飛来し、ゆっくりと鳴き始める。その鳴き声はかなりの距離までとどき、いつも五、六人の少年が同時に飛びだして来る。特にススム少年の家よりもっと奥に入った空き地には、適当な間隔で二本の青桐が植わっていて、ここにはひっきりなしに蝉が飛来する。総じて油蝉が多いが、時にはミンミン蝉があの鼻づまりの大声を響かせることもあるし、小さなニイニイ蝉のか細い声が聞こえることもある。夕方日差しが弱まる頃、ヒグラシが静かに夕暮れを伝えることもある。少年たちの反応が強いのは、何と言っても油蝉とミンミンであろう。極く稀に「ジャアジャア」と聞き慣れぬ大声で鳴く熊蝉は例外である。しかし青桐に留まった蝉を捕るのは至難の技である。蝉も利口で幹の上方に留まることが多く、相当長い竿を付けなければ網が届かない。登って手で捕るのは尚更困難である。真っ直ぐに立ち、蝋を塗ったようにつるつる滑る幹には手掛かり足掛かりになる枝も無く登るのが難しい。がき大将が面目にかけて挑んでも、尻を大きく振って登らざるを得ず、その振動で蝉は逃げてしまう。やはりチャンスは少し隅の方に立つクヌギやモチの木に留まった時である。ススム少年には蝉がどの木に留まったのかを家の中に居ながら見当をつけることが出来た。
「来た、あの木だ。」
少年は弾かれたように玄関を飛び出す。あっという間に木の下に立っているが、その頃は蝉の恍惚感は絶頂に達し、少しぐらいの木の揺れには反応しない。この頃、少年は蝉の声に立つ時には網を手にすることはない。初めから登って手で捕るつもりでいる。何と言ってもこれが最高の醍醐味だと少年の全感覚が覚えてしまったのだ。
一番下の枝に足が掛かる頃、蝉の声に力が無くなる。要注意である。少年はぴたりと動きを止め、なりを潜めて幹に張り付いてしまう。蝉は声を途切らせたり、吃るように鳴いたりして様子を窺っているが、再び安心して朗々たる音響が復活する。少年は再び登攀を開始して、二の枝、三の枝へと前進。これを繰り返すこと数分。余り時間を掛けては蝉が飛び立ってしまう。といって焦ってはならない。蝉の声で彼の警戒心を推し量り、接近に接近を重ねるのである。最後に手を無理なく伸ばして蝉の背中から覆い被せるように捕獲するのだ。この瞬間がすべてであると少年は感じている。そしてこの瞬間こそ蝉の恍惚感の絶頂を狙わなければならないのだった。これは絶妙なタイミングであった。それでも三回に二回は取り逃がしてしまう。その上、蝉の排泄物を嫌と言う程顔に浴びせられる羽目になる。蝉の鳴き声のサイクルは五回か六回が限度であるから、素早く登り着くことも絶対条件であった。掴み捕りに成功して、手の中に激しく悶える蝉の翅の抵抗を、目眩いにも似た満足感を持って実感する時、蝉の声はもはやリズムを失い、ただ騒がしい狼狽の声に変わっていた。
少年が蝉の捕獲法を「掴み捕り」だけにしたのには理由があった。その頃、少年は慢性の吹き出物に悩まされていた。それも悪性のもので、腫れがとことん熟して膿をはらみ、骨近くまで深く根を張り、白黄色に固まった根が幾つも除去されるようになって初めて治癒へと向かうのであった。頭から始まり、頸、腕、横腹、尻、脛と次第に下へと部位を移し、踵の横で飛びきり悪性のものが消滅するまで続いたが、それが一通り終わると嘘のように消えて二度と現れなかった。その最中母はそれを「お前が虫を捕るからだ。」と断定した。虫の祟りだと言うのである。確かに初めの頃、捕獲が原因で死んでしまった昆虫もいたが他の子供たちに較べれば、蟲の死にはこだわる少年であった。しかしこの母の言葉が少年と蟲との関係を決定的に変えてしまった。昆虫を捕り続けることは止めなかったが、勝負がついてしまった後は、直ちに蟲を自然に戻してやった。籠に入れることも、標本にすることも止めた。「銀茶来い」という雌の「茶」を紐につけて飛ばし、雄の「銀」をつがわせて生け捕りにするやり方も、性的な匂いも含めて子供らには人気があったが、少年は、鮎の友釣りと同じに、囮として使い殺されてしまう雌の「茶」が哀れで、耐えがたい嫌悪を抱いた。少年の心には、蟲の「人格」がいつか住み着くようになっていた。
N駅から北へ足を伸ばし、少年の家への路地を曲がらずまっすぐに春日神社の方へ進むと、舗装道路を挟んで両側に網のように広がる稲田が見えて来る。畦道が作りだしている模様が風景に落ち着きを見せ、奥行きを豊かにしている。まだ水が張られていない早春の季節には、蓮華の花のピンクの絨毯が敷きつめられ、所々に散在している菜の花畑の黄色と映えて、可憐な春の色彩を放つ。その中に幼い子供らが自由に入り込んで蓮華の花を摘み、花冠を編んでうち興じている。田植えが終わり、田の水に稲の早苗が影を映す頃には、きかん坊たちが、オタマジャクシやエビカニを捕りに集まって来るし、秋の実りが黄金の波を打ち寄せる季節には、家族総出でイナゴ捕りに余念のない人々も見受けられた。
この稲田の広がる中央に、こんもりと繁っている神社の森を囲むように弧を描いて河が流れていた。その河を渡る道が尽きると、そこには古びた朱塗りの鳥居と小さな太鼓橋があった。河の両岸は草深く、暗い岸辺を水面に映し、河は鈍く黒く流れていた。草むらには、細長い胴を夜光塗料のような怪しげな緑に染め、真っ黒な翅をゆらゆらと動かせゆっくり羽ばたきながら、頼り無げに飛び交っている変わり種のトンボが見える。「お羽黒トンボ」と子供らは呼んでいた。神社の傍という場所柄や、その陰気な姿に、ススム少年も、何か不気味なものを感じて、「お羽黒」には近づこうとはしなかった。それよりもこの河には大型のエビカニが棲息していて、蛙の肉などを餌にして釣り上げている者も居たが、主に高学年の男の子が多かったのと、蛙の肉で餌を作るのが残酷で、少年は馴染むことが出来なかった。少年はせいぜい田んぼの畦道で、小さなエビカニや、オタマジャクシを相手に時間を過ごすのだった。オタマジャクシを持ち帰り、やがて後足が出、前足が生えて来て、尻尾が消え、丸い体が四角く大きくなり、蛙へと変貌して行く様を、何度も何度も驚異をもって見守ったものだ。時には、自分の体が変化して別の生物へと化身する夢まで見たことがある。少年は感情移入の激しい性格だったのかも知れない。イナゴを食用にすることも出来なかった。佃煮になったものも大人になるまでは手を付けることはなかった。
(三)
ススム少年の蟲に対する関心はその対象によって微妙な違いがあった。トンボや蝉には友達のような親近感があったが、クモやカマキリなどには近寄り難い壁があって、その壁が逆に一歩退いた好奇心を増大させ、やや残虐な苛め気分を生んだ。
兵隊蜘蛛が庭木の枝から、軒先へと大きく巣をかけ、何やら呪文めいた太字の記号を書き込んで、その中央に細い足を長々と伸ばして餌待ちをしているのを見ると、黒と黄色の艶やかな輝きにも係わらず、むくむくと対抗心が沸き起こって来て、巣に枯れ葉を投げてクモの慌てた対応振りを笑ってやりたくなった。棒でつついて、巣の一部を破壊したり、巣を支えている糸を一本ずつ切って行って、ついにはクモが体の重みを支えることができず、形の崩れた網を体に巻きつけるようにして地上に落下して行くこともあった。
クモの中には、土蜘蛛といって、木の根や家の土台の地面すれすれの所から地中に繊維質の細長い袋を埋め込んで、その中に棲息しているものがいた。繊維質は脆く、注意してそっと引き抜かないと、地中にクモを残して切れてしまう。少年は慣れてくるうちに、そのコツを覚えた。巧くクモごと引き抜いたにしても、別にクモをどうこうする訳ではなく、クモは狼藉者に正体を暴かれ、自分の袋から抜け出すと、あたふたと植え込みや縁の下へと逃げ込んで行くだけであった。
カマキリに出会った時には、少年はどうしてもその前を素通りすることができず、立ち止まって、その動向を注視した。カマの構え方、目玉の動かし方、頸の傾げ方、怒った時の胸の反らせ方から、やおら翅を広げて威嚇の態勢に入るところまで、生態の細部を読み取った。少年はカマキリには手を触れることがなかった。それはカマが怖いからではなく、かって気味の悪い光景を目撃してからのことである。他の子供に悪戯でもされたのか、翅を歪め、腹の一部を潰されて、地面に這いつくばっていたのを発見したのである。いつものように少年はその場にしゃがみ込みじっと目を据えた。カマキリの腹がぴくぴく動いていた。尻の先からやや薄黒い針金のようなものが見えていた。初めての経験であった。奇妙に思えて、少年は傍に落ちていた枯れ木の棒を拾い上げて、その部分をつついて見た。すると突き出ていた針金のようなものが、するすると伸び、あっと言う間に渦を巻きながらカマキリの体内から完全に脱出したのだった。少年は、思わず飛び退いて声を立てた。
「何だ、これ。」
こんな経験は、この時一度だけであった。しかしその時の異様な驚きには忘れることのできない強烈さがあった。後で誰かに、それが「針金蟲」であってカマキリの寄生虫であると説明を受けたが、その真偽は判らないまま、驚きだけが残った。どんな生き物にも凄い敵がいて、体の中にまで侵入することがあるのを実感で学んだのである。
アルミサッシュというような建材がなく、網戸も高級な家屋でなければ付いてはいなかったので、夏などの季節には開け放った窓や縁側から好きなだけ蟲が入り込んだ。夜、明かりを求めて、カナブンと呼んでいたコガネムシ、スイッチョやクビキリなどのばった類、さらに薄翅かげろう、米つき蟲、風船蟲など様々な昆虫が飛び込んで来ては、電気の傘にぶつかって落ちて来たり、蚊帳に止まって鳴き声を立てたりした。カナブンは大きな騒々しい翅音を立てて部屋中を飛び回った。蚊帳の麻の生地に止まって「すいっちょ、すいっちょ」となく小さめの緑の蟲には季節感と風情が感じられたものだ。鳴き声を「チョンギー」と表現する者もいた。これとよく似た蟲に俗称「クビキリ」と呼ばれるバッタがいたが、この蟲は何故か噛みつくと放さない習性があって、蚊帳に食いつかせておいて体を引っ張ると、訳なく頸が胴体を離れてしまう。その呼び名もそこから付いたものらしい。子供達にはこんな残虐な遊びを好む一面もあったようだ。少年も何回かはやったことがあり、頸の切れ目がひくひく動くのを夢にまで見た。この蟲が鳴くのだけは少年も確認していない。だから、鳴くのがスイッチョで、鳴かない大きめの物がクビキリだと区別していた。
可愛いのは風船蟲と米つきバッタである。「米つき」の方は、名前に反してバッタの類ではなく、黒く固い翅で防備した二センチ程の昆虫である。では何故バッタと呼ぶのかというと、この蟲を仰向けにして寝かせると、しばらく身を固めていてから、やおらパッチンと音を立てて跳ね返るのだ。その様子からバッタのように呼ばれてしまったらしい。
もっと愛らしいのは風船蟲だ。体長五ミリ程度の羽虫だから、飛んでいる時には目に付かない。何かに当たって新聞紙などの上に、ハラリと落ちてくる。少年は、これをまず見逃すことはない。いつも何匹か連れ立って落ちてくるところを見ると、どうやら数匹固まって飛んでいるらしい。少年はすぐさまつまみ上げて、コップに水を張りその中に全部落とし込む。新しい環境に馴染まないうちは、コップの底か、横に静かに吸いついていて離れない。少年は、新聞紙の端を指で小さく四角形に千切り取ってコップの中にいれてやる。紙が水を吸い、重くなると底へ沈んで行く。すると今まで静かだった虫たちは突如運動を開始する。蟲は泳ぎだして、底にある紙片に止まると自分の浮力でそれを持ったまま、水面まで浮き上がるのである。水面に達するやたちどころにその紙片を放り出して、再び水底まで潜り、別の紙片に止まる。そしてまたもや天国に登って行くのである。この繰り返しなのだ。少年はこの蟲を「郵便屋さん」と命名した。
カナブンは体の大きさの割には力持ちである。子供の中には木綿糸を結びつけて玩具の車などを引かせようとする者もいた。明かりを慕って飛び込んできて、あちこち激しくぶつかっては音を立てて落ち、捕獲されて荷役を強いられてはたまったものではない。しかし朝になって一番目立って日溜まりに死骸を曝しているのは彼らだったようである。
カナブンを余り苛めなかったススム少年もカブトムシには並々ならぬ興味と憧憬とを抱いていた。特に雄の角の力強さには抗しがたい魅惑を感じていた。黒光りのする体についた大きな頭部、そこから不思議な線を描いてニョッキリとそそり立つ角。その根元には、これまた黒々と輝く球状の目玉が、ある種の宝石の様に輝いていた。少年は角に糸を掛けてその先に玩具の車類を繋げ、黒い固い体を指で弾いては蟲を励ますのだった。蟲は荷が重くなってくると、後ろを振り返って、何を引かされているのかを確かめるようにしてから、また「ウンコラショ」とばかりに引き始めるのであった。蟲が少し弱ってくると、わざわざ三十分もかけて、初めにカブトムシを捕獲したクヌギ林まで足を運び、巣に好適な樹の洞を見つけて放してやった。その替わりにテカテカと光った樹液を存分に吸って力に満ちた新しい友達を連れて帰って来た。日向の縁側は少年とカブトムシとの良きグランドであった。
(四)
愛すべき蟲達との出会いは、異様な儀式で出迎えてくれたこの地の友人たちと親しくなるきっかけをも与えてくれた。子供達独り独りの好みは様々であったが、蟲への愛着という点では共通していたので、いつも何人か連れ立って繰り出して行ったものだ。当然仲間は固定化してきて、仲良しのグループもできた。するとその母親同志も親しくなり、情報交換をするようになり、時には子供たちの遊びが度を越したりすると、申し合わせて圧力をかけて来ることもあった。子供たちの関心は次第に蟲を相手にすることよりも友達同志の付き合いに傾きつつあった。そんな年頃になっていたのであろう。
この地に移って来た頃、向かいの家に「軍人さん」が住んでいた。新婚家庭であった。若い奥さんは少年の母親と親しくしていて、折りにふれ土産物のやりとりなどしていた。軍服を着たご主人は見るからに立派で、少年には特上のカブトムシのように感じられた。ススムには二人の兄と妹が一人居た。子供の居なかったこの夫婦は、はにかみ屋の反面どこか人なつこいススムだけを家に上げてはお菓子を食べさせ、何かと世話をやいた。若い奥さんの仕草や声は、母親とは違う柔らかみを少年に感じさせた。しかし仲間の子供たちがそれに嫉妬していることを知って以来少年はかたくなに家にあがるのを拒んだ。若夫婦は少年の突然の変心に狼狽したが、母親の言い訳のせいか、その後は家に呼ばれることはなくなった。
その家の左隣にミツコという同級生がいた。学校の行き帰りは何かと話掛けてきたが、これも男の仲間達の冷やかしの声が大きくなるにつれて遠ざかって行った。
路地のどん詰まりの家のサチコは末っ子で、妹のタエコと同級であった。彼女は毎日のように少年の家に遊びに来ていて、少年を「オニイチャン」と呼んですっかりなついていた。少年ももう一人の妹のように可愛がっていたが、いつからか急によそよそしくススムを避け始めた。後で判ったことだが、「水雷艦長」の遊びの最中サチコのすぐ上の、きかん坊の次兄とトラブルが起きた時に、上級生である長兄が弟の声を聞きつけ、家から飛び出して来て、やおらススムの頬を張ったのである。長兄は学校でも力の強いのでは評判だった生徒なので、ススムの体は立ちどころに地面に這いつくばった。それ以来サチコはススムの家に上がり込むことはなくなった。「いいじゃんか。」「そうじゃんか。」と日頃連発していた静岡の「ジャンカ」言葉も聞かれなくなった。
西隣のチエには少年は早くから仄かな甘い感情を抱いていた。おとなしく控えめな性格、甘えるような少年への語りかけ、白く柔らかな肌など、少女を身近に意識すると突然自分が「不良」になってしまうような一種の罪悪感に襲われたものだった。自分の家の庭に防空壕を掘るゆとりのない家庭では避難訓練の時、近くの家に分散して避難するようになっていた。そんな時、チエは少年の家の防空壕に避難しに来たことがあった。大人たちが遅れ、まだ二人だけであった時、チエは怖がって少年に抱きつくように寄り添って来た。少し受け口のチエの唇が少年の腹のあたりでシャツの上から熱い息と共に、微かに震えているのが伝わって来た時、思わずしっかりと抱きしめて、お下げの髪に頬ずりをせずにはおれなかった。少年の胸は高鳴り、血が全身を走り回っていた。不思議そうな顔を仰向け、脅えの浮かんだ目を少年に向けると、黙って体を振りほどいて防空壕を飛びだして行った。それ以後チエの家族は少年の家の防空壕を利用しなくなり、近所にはしばらくの間ススムについての性的な悪評判が流れていた。ススムの体と心には性の自覚を促す自然の力に圧倒されて、好奇心と罪悪感が軋み合いながら渦巻いて流れていた。性の違いとは何なのか、女の子のスカートの下には何があるのか。大人たちがいやらしい笑いを浮かべてそれとなく話題にしている、あの何かが気になってならなかった。スカート捲りなどを屈託なくやれる歳はもう過ぎていたのだ。裏の畑道を抜けて来た女の子を捕まえて、パンツを脱いで性器を見せるよう強いた事が一度だけある。頭の中が炎のように燃え上がり、自分が殺人でも犯そうとしている罪悪感で指が震えていた。少女の股間に何があったのかもまるで覚えがなく、そこには恐ろしい蟲が巣を作ってでもいるかのように「わっ。」と声をあげるとその場を逃げ去った。このことも口伝えに近所に広まったのであろう。女の子達は少年を見ると、あからさまに嫌悪の表情を浮かべて逃げ去った。こうして蟲も女の子も離れて、少年は荒々しい男の子の世界へと追われて行くことになった。
(五)
下の畑の中央を左右に走る道を左に抜け、朝鮮長屋(朝鮮人ばかりが固まって住んでいる長屋をこのあたりではそう呼んでいた)の前で舗装道路を右へ五、六分行くと、右側に大きな氷倉のある製氷会社があった。ケイタの家である。倉庫の横手にまだ建てて間もない住居があった。ケイタは学校から帰ると、「只今。」と一声怒鳴って靴も脱ごうとせず、鞄を上がりかまちに放り出すと一目散に走りだす。
風が強かった。シャツの袖が腋の下で「ビ、ビ、ビ」と音を立てた。舗装道路を左に曲がる所で風のために大きくシャツが膨らみ、曲がりきれずに危うく転倒するところであった。畑を貫く小道は一層風が激しく、体は否応もなく反り返った。ズボンのポケットではずしりと重いベイゴマが互いにぶつかってかちかちと音を立てながら、ケイタと共に走っているようであった。途中から畦道に飛び下りて真っ直ぐ、ススムの家の裏手へと駆け上がる。「今日は、負けねえぞ。」ケイタが呻くように呟く。
「先生の見回りはねえだろうな。」
「角田の奴、うるせえんだ。」
「この間は八個も取り上げられちまった。」
「俺もよ。太田の奴に、缶ごと没収だ。そばにあったメンコまでみんなだ。」
ススム少年の家の玄関の土間は少年たちの異様な熱気で蒸れかえっていた。
いわゆるベイゴマという遊びは、メンコ同様、物をやりとりするという理由で学校からは固く禁じられており、見つかればその場で没収された。教師達は自転車で見回りを行い、学校の意思の強さを見せつけた。親たちもこれに協力する者が多く、「トコ」を中央に数名の子供らが集まれる場所は、一つ一つ潰されて行ったのだった。まるで大人の世界の賭場の取り締まりのようであった。ススムの家は、父親は勤めに忙しくこうした問題に口を出す暇などなく、母親は移住者の弱みからか、子供たちの付き合いには寛大であった。勉強にも遊びにもうるさいことは言わず、むしろ「他が駄目なら内でやりなさい」という具合だった。
学校で、「今日やるぞ。」となると、ススムは一早く帰宅し、庭の縁側の下に隠してあるバケツとカッパの布地を持ち出して来る。玄関土間の真ん中にバケツを置き、カッパを被せてぐるりを紐で固定し、布地に水を口から吹きつける。日頃、畳屋さんの仕事ぶりを見守っているのであろう。堂に入ったものである。濡れた布地がしっとりと落ち着きを見せる頃、一人二人と悪童達が集まって来る。入って来ると、彼らは誇らしげに、小箱や缶の中から、自慢のベイゴマを取り出す。大小の巻き貝形をした鉄のコマで、上部には色の付いた蝋が流し込まれていて、様々な模様が描かれている。その周囲にはかなり大胆な細工が施されている。グラインダーなどの機械が身近にある者は、それを使うが、大方は怒鳴られるのを覚悟の上で、近くの「お大臣」などと呼ばれている大きなお屋敷を取り囲むコンクリートの塀に、弧を描いてコマを擦りつけ、時間をかけて擦り減らすのである。「お大臣」からは再三学校の方へ抗議が来るが、子供等にとっては格好の砥石だったのである。これは廻っている時に、相手のコマに打撃を与えるコマを作るために必要な作業だったのだ。5角か6角位が標準で、故意にアンバランスな削り方をして、回転持続力を犠牲にしてまでその打撃力を強める者も居た。また胴の部分を苦労して擦り潰して平べったい形に変形させ、上向きの角を付けていわゆる「ペチャ」なるコマを作る者も居る。敵の下から潜り込んで攻め上げ、弾き出す、新兵器である。一つ一つが彼らの傑作であり、愛着も深い。ゲーム中に客観的な評価を得たコマは、特別な名前で呼ばれるようになり、それを倒す強力なコマを作ろうと血眼になるのであった。常に審判は参加している子供たちの目そのものである。勝負は彼らの見守る中で、正々堂々と行われた。
「ホーイ、遅くなったぜ。」
大声がして、ケイタが飛び込んで来た。
「お前、残り勉強させられてたんだろう。」イタチが声をかけた。イタチは太一のあだ名で、ススムたちの住む区画の隣に建つ長屋の一隅に住んでいた。
「角田の奴、俺ばっかり目の仇にするんだぜ。そんなこといいから、仲間に入れろ。」
ケイタはもう紐を口にくわえていた。紐の端を持って、紐全体が口の中を通り十分に唾液で湿りがつくように、反対側の端が口の中で留まるまで滑らかにしごいた。と思う間もなく結び目が二つ出来ている端を、コマが立つ先端にあてがい、手首をくるっと廻すとあっという間に紐をコマの傾斜面一杯に巻きつけていた。右手の小指と薬指の間からは紐の末端がわずかにはみ出ていて、大きな結び目が指の股にしっかりと挟まっていた。
「よし。行くぞ。」五人程が応じた。
「チッチのチッ」
掛け声に合わせて、黒い小さな固まりが、どすっと音を立てて、「トコ」に叩きつけられた。一つだけは、大きく弧を描いて「トコ」の外に弾け飛んだが、残りはすべて見事に唸りを上げてぶつかり合った。薄暗くなると火花さえ飛ぶことがある。イタチの「ペチャ」が、一回り大きなケイタのコマを下から攻め上げ、「トコ」の淵まで追い込んだが、縁ぎりぎりの所で、逆に自分から飛び出すように弾け出てしまった。ケイタの「デカ」は「トコ」の中央に再び降りながら、ススムの「はやぶさ」が傾いて隙の出来た側に回り込み、それを一気に押し気味に弾き出していた。残ったコマの勢いが衰え、勝負が終了したのを見た他の子供たちは、てんでに自分のコマをすくい上げた。
「やったぜ、やったぜ。」ケイタは喜びの声を上げて、外に飛びだして土間の隅に転がっている「ペチャ」と「はやぶさ」を拾い上げた。「はやぶさ」はススム自慢の、そして仲間達羨望のコマだったのである。
ベイゴマ以外にも幾つもの遊びがあった。クギ差し、めんこ、ビー玉。キャッチボールの道具もなかった時代なので、ヤジリ代わりにクギを差し込んだ篠竹に紙の矢羽根を付けて相手に投げつけると、相手はそれを素手で握り止めて投げ返すという物騒な遊びも考案されていた。勿論女の子達は、縄跳び、一面二面、ゴム紐飛び、ハナイチモンメ等、女の子らしい遊びを楽しんでいた。戦争ごっこにルールを取り入れた「水雷艦長」という遊びが流行って、少年たちは狭い露地に二つの陣を構えて走り廻ったものだが、空襲が頻繁になると本物の空襲が遊びの代わりになるのか、本物の遊びは影を潜めるようになった。
「ウー、ウー、ウー」とサイレンが神経を逆撫でするように断続音を響かせ、敵機の襲来を告げる。それが日常茶飯事となって来ると、市民が、飛行機雲を短く引きずったB29の飛来を先に肉眼で見つけ、おかしいぞと思っているとサイレンが鳴りだすといった呑気な場面すら見られるようになった。権威ある大本営発表も軍管区情報も当てにならず、市民の方も慣れっこになると、初めはサイレンと同時に防空壕に飛び込んでいたのが、まだ平気とばかり仕事を続け、グラマン等艦上機の機銃掃射が突如「バリバリッ」と屋根をめくるような音を立て始めてやっと泡を食って壕の入口に転げ込むことさえあるようになった。ススムの両親も掃除の仕方が悪いと言ってやり直し始めた父親に母親が言い返して、声が段々高まるのを、ススムがはらはらしながら防空壕の入口で聞き耳を立ててこわごわ外を窺っていることもあった。親たちはぎりぎりまで言い争っていて、南側の森の上に聳えている欅の大木を回り込むように旋回した艦上機グラマンが轟音とともに急降下しながら屋根のトタン板を毟り取るような音をたてて発砲を始めた時に二人は東側の縁側から壕の中へ転げ込んで来た。二人はもつれて壕の底に倒れた。無意識に頭を抱えていた。それでもなお口の中でぶつくさと何やら呟いていた。ススムはそれでもホッとした。遙か神社の方角で「ドスーン」という重い地響きがして、壕の側壁が揺れ、細かな土くれがパラパラと崩れ落ちた。
その頃になると、夜となく昼となく空襲が続いた。市民の神経を疲れさす作戦だろうと言われていた。事実、ススムのような小学生(正式には国民学校の生徒と呼ばれていたが)でさえ、ゲートル(兵隊用の巻脚絆)を脚に巻いたまま床についた。二日程たって解くと脚は白くふやけ、ゲートルの巻き跡が付いていた。
少しずつ慣れて来ると、始めは恐怖で空を仰ぐことすら出来なかったのが、ススムも両翼をピンと反らせて銀色に輝くB29の大編隊が、その一機ごとに短くしかし鮮やかに飛行機雲を引きずっているのを見て、見事な風景を見る思いであった。赤トンボの大群を抜けるような夏空を背景に眺めた時と同じであった。鬼ヤンマを迎え撃つあのときめきすら感じられた。恐ろしい戦争の道具には思えなかったのである。しかしその都度たくさんの家が焼かれ、死者を出した。ときめきはいつも恐怖に塗りかえられるのであった。
(六)
ある晩、ススムの両親が「縁故」とか「集団」とかいう言葉を何度も繰り返しながら、暗い声で話し合っているのが隣室から聞こえて来た。
学童の中から空襲の被害者が出るようになり、本土決戦などという言葉が口に出るようになって、国は小学生を身寄りがあれば縁故で、田舎がなければ学校ごとの集団で地方に疎開させる方針を決定した。学校からは各家庭の決意を促す意味もあるのか、どちらにするかを答えさせる刷り物が配付されていた。
ススムの家では、余り親しい付き合いを続けているとも思えない親戚が、福島にあるにはあった。そんな細いつながりを頼るよりましと考えて、父親は、勤めている役所の仲間と図って、福島の山林を入手して、疎開と開拓をかねて田舎に引きこもる計画を立てていたようだった。既に荷物の一部は送ってあるらしかったが、計画が進捗せず、食器などは送り返されて来た。未だ仲間うちの合意に不安があるらしく、母親との父の会話にはいまいち歯切れの悪さが残った。それに敏感に反応してか母親の気持ちや言葉にも不安が重くのしかかっていた。
「やっぱり今までの準備は無駄だったのね。甘いんだから、お父さんは。」
「しょうがないだろう。相手があってやっている事なんだから。」
「返ってきた荷物だって、食器類なんか、割れていたりして、大変。どうせこうなるなら、初めから集団疎開に決めておけば良かった。」
ススムは、そうかやっぱり妙義山に行くんだ、と思った。第一陣で妙義に疎開した腕白なショウイチの顔を思い出していた。生徒の半数近くが縁故で疎開し、ベイゴマ仲間のケイタ達も、近所のサチコも、都心から転校して来てススムをからかってはよく声を立てて笑うおしゃまなカヨも縁故疎開で姿を消した。カヨは別れの日に、小さな紙切れをススムに手渡した。紙には「妹さんの名前で私にお手紙下さい。必ずね。」と書かれていた。ススムの胸は高鳴り、顔が熱くなった。
ススムの学校の集団疎開は前年(一九四四年)八月に一陣が、そしてかなり多数が参加して第二陣がこの四月に出発したばかりであった。もう残っている生徒は僅かになっていて、学校はすっかり教育機能を失っていた。
「大丈夫だよ。僕、妙義に行くよ。平気だよ。」
ススムは親たちの暗さが悲しかった。未知の世界に踏み込む怖さはあったが、こうして暗く東京にいるより、好奇心で不安を吹き飛ばす方がどれだけましか知れない。母親が顔を向こうに向けたまま目頭を押さえているのがわかった。父親は顔をくしゃくしゃにして、がんばるんだな、とだけ呟いた。
第二陣に数週間遅れて「追加参加グループ」としてススムは妹のタエコと、ススムと同期の女生徒浅井ミヤ、それにタエコと同級の双子の姉妹、水谷サエとチヨの五人が、ススムの父親に引率される形で、上野駅から人間の体と荷物がぶつかり合ってごった返している列車へと乗り込んだ。汽車に乗り込むにも入口はぎっしりと詰まっていて新たな客のために道を開けることなど不可能であった。従って中にゆとりが有りそうに見える窓を選び、父親が子供らを抱きかかえると足の方から乗客の隙間へと割り込ませて行く。中からは「もうダメだ。もう入らねえよ。」と怒鳴り声が返って来るが、それでも少しずつ体が納まって行くのが不思議であった。その手で父親は五人を中に押し込んだ。女の子の悲鳴が回りの乗客の譲歩を促しているようだった。こんな状況を予想して、学校は信頼のおける同行者を探していたのだが、丁度ススムの父親がその役を担ってくれることになり、全権を委ねていたようだ。学校側にはもう付添いを出す人的ゆとりはなく、教員たちも既に四散していた。
やっとの思いで上野を発ったものの、高崎に着くまで途中で二度空襲を受け、何度も臨時停車を繰り返した。機銃掃射や爆撃を直接受けないだけでも幸せと思わねばならなかった。松井田に着くと、先発で疎開した子供らが数名迎えに出ていた。寮のある妙義山麓まで桑畑の中を先導する任務を帯びて来たのだが、子供らには落ち着きがなく、何度も途中で休みたがった。そしてその都度「にぎり飯残ってねえか」とか「何か食い物持って来たか」とか、しきりに食べ物を催促する素振りを見せた。そして終始体のあちこちをボリボリと掻きむしっていた。いかにも痒そうであった。
寮に着くと、寮生たちが三々五々玄関の框に姿を見せ、やがてその数も増えて新入りを囲むようにして迎えた。肌や衣服の汚れ、目の光など明らかに異質なものを感じさせた。ススムはN駅の家に引っ越して来た時の、あの異様な経験を思い出していた。あの脅えとも威嚇とも思える眼光が、ここにもあった。ススムは何もが見慣れぬ環境の中で、自分の体が萎縮して行くのを感じていた。
「まあまあ、お疲れさん。どうぞ上がって下さい。」
女の声がして、突き当たりの帳場の奥にある部屋から、宿の女将らしい女が出て来た。その後ろから、子供らの世話をする寮母も二人出て来た。一人は丸顔の太った若い女性で、いかにもこの土地の人間らしい素朴さを漂わせていた。まだ笑顔に子供っぽさが残っていた。もう一人は、色の白い、一見都会人の印象を受ける、少し上の年輩の女性であった。
「さあさ、お父さん、ひとまず茶の間でご挨拶せねば。」
女将の案内で、新入りの子供達とススムの父親は帳場を通り抜けて、茶の間に通された。父親の挨拶に続いて、寮母や宿の女将の自己紹介があり、子供達も口の中でもごもごと自分の名前だけをやっと言った。そこに寮長の太田先生が姿を見せた。やせぎすな体、額に皺が深く刻まれた彫りの深い風貌は、子供らにはいかにも厳しさを感じさせたであろう。
「いやあ、ご苦労さまでした。途中大変だったでしょう。汽車はどうでした。空襲はどうでした。」
厳めしい顔のわりには愛想の良い言葉が飛びだした。父親が手短に車内の様子や、空襲の状況などを説明すると、寮長は、頷きながら言った。
「じゃ、子供らは、部屋に行って、班の友達と一緒に行動しなさい。」
部屋の外の廊下にたむろしていた子供らに囲まれるようにして、五人の新入り寮生達はそれぞれの部屋へと分かれて行った。
(七)
何かの鳥が無数に囀っているような気がして、ススムが目を覚ました時、山麓の清々しい空気が縁側のガラス戸と部屋の障子とを通してススムの額の辺りまでひたひたと届いているように思えた。十畳間の一班の部屋では、他の子供たちが、思い思いの向きに布団からはみ出したり、薄い掛け布団を頭からすっぽり被ったりして寝息を立てていた。
今日はこの寮の生徒代表として、神社での朝礼で三つの寮から集まって来る三つの学校の生徒たち全員に号令を掛け、朝礼を進行させるという大役が、ススムの神経を緊張させていた。そのせいで予定の時間よりも早く目覚めてしまったようだ。
「何時だろう。」
トイレに寄るついでに玄関の太い柱に並んで置かれている大時計を見ると、まだ五時半を少し廻った所であった。
「まだ早いんだ。」
ススムはもう一度寝床にもぐり込むと大きなアクビをした。
父親に連れられてここに来てもう二か月以上が経っていた。大方の生活習慣にはもう慣れて、一班の生徒十人の責任者として、また、対外的にはこの寮の生徒代表としての仕事を寮長から任せられていた。
今では妙義山麓にある三つの旅館が、学童集団疎開の施設に当てられ、東京の三つの小学校(当時の国民学校)の生徒が収容されていた。初めは、ススムのいる寮を三校が共同で使っていたが、第二陣の疎開で参加する生徒数が大きく増え、それぞれ学校ごとの寮に分かれたのであった。一緒の頃は、各学校の番長格の生徒同士が凌ぎを削るような場面もあったが、これでそんなトラブルもなくなった。しかし、ススムがこの寮に入った時、番を張っていた生徒がいて、ススムに決闘を挑んで来た事があった。子供の世界にも新旧の面子があった。何やら新入りが先生の後押しで一班の班長になったり、生徒代表に据えられたりするのは旧勢力にとっては耐えがたい屈辱であった。
「ショウイチが、お前と話をつけると言ってる。」とショウイチの子分イチローがススムに告げた。
集団疎開第一陣から参加していたショウイチが男子全体を「仕切って」いることはススムもよく知っていた。
「話って、何の?」
イチローは、ボクシングの仕草をして、ニヤッと笑った。
あちこちに伝令が飛び、廊下に何人かの見張りを立て、廊下側の障子を締め切って、一班から三班まで三つの部屋をぶち抜いて大広間にした。いつの間にか、男子生徒の全員が、まさに例外なく全員がこの決闘場に集まって来た。見物しなければならない行事だったのである。
ススムは、このような世界にはこれまで全く無縁で、喧嘩らしいものは苦手であった。特に殴り合いの喧嘩などは恐ろしくて一度も体験がなかった。目を腫らしたり、歯を折ったりする位なら、謝って逃げたほうがましだと思っていた。意気地のない少年だったのである。かって虱がついていない新入りとは一緒には遊べないと仲間外れにされた時も、ススムは自分から虱を一匹貰って大切そうに肌着につけておいた。虫はすぐに増えた。不潔な寮生活では、なにもこんな事をせずともすぐに下着の縫い目には虱の行列が見られるようになることに、ススムは気づかなかったのだ。卑屈な譲歩がススムの「社会参加」を確実なものにした。ススムは虱の住み着いたシャツを持って、仲間たちに見せて歩いたものだった。
決闘宣言を突きつけられた時、嫌な予感はしたが、自分が何も悪いことをしていないのだからそんなに酷いことは起こる筈はないと思い込んでいた。しかし、気がつくとススムとショウイチは、ボクシングのリング上のように円を描いて取り囲んだ仲間達の目の前に押し出されていた。
ショウイチは周りの仲間達の目を明らかに意識して、闘争心を露らわにして見せるジェスチャーをし、目を剥きだしてススムを睨み据えた。拳の構えは奇妙なもので、左腕を真っ直ぐ前に突き出し、右の拳を胸元に引きつけ、片目を細めて狙いを付け、じりじりと詰め寄って来ては、突然横っ飛びに跳び退いたりした。ススムの方はただ木偶のように両腕をだらりと下げたまま突っ立っているだけだった。この様子を見て、にやりと笑ったショウイチはぴょんぴょんと何度か跳ねた後、いきなり右の拳を思い切り突き出して来た。身を翻す術も知らないススムは頭を下げて石頭にげんこつを受けると、そのままの姿勢でショウイチにぶつかって行った。ショウイチは予想もしなかったススムの対応に右手が痺れ、怯むところに大きなススムの頭がショウイチの眉間を襲った形になった。吹き出した鼻血が彼の顔面を染め、その場にうずくまってしまった。意外な結果に、取り巻く少年たちはざわめきを残して、二人、三人と、何やら囁き合いながら立ち去って行った。イチローだけがそばでおろおろしていた。ススムは初めて人を傷つけた罪悪感に戸惑い、ショウイチの傍に立ちすくんでいたが、自分のタオルを取って来て、黙って挑戦者に差し出したのだった。
うとうとと再び浅い眠りの中をたゆたっていたススムは、ラッパ手リョウタの吹く起床ラッパの音で飛び起きた。周り中の子供らが眠そうに顔をしかめ、寝返りを打ちながら上半身を起こし始めた。ススムが大声で「起床」と叫ぶ。あちこちで布団の片付けが始まり、押し入れの戸が開けられる。あまりきちんと畳めていない布団もあるが、何とか押し入れに納まって行く。部屋の隅の布団の上で、小柄な少年が一人だけ座ったままベソをかいていた。二年生のテツオだ。疎開に参加するのは三年以上であったが、家の事情もあって一人だけ二年生が混ざっていた。五年生の兄が一緒ということで特別に認められたのであった。
「テツオの奴、またやった。」
「また地図描いたのか。」
一班の仲間がはやし立てた。ススムが駆け寄って、テツオの手を取って立ち上がらせ、汚れた下着を脱がせた。尻を一つ派手に音を立てて叩くと、「下着を替えて来い。他の奴は見物してないで、布団を廊下に乾せ。」と命じた。鼻を摘む真似をして茶化しながら、三人程が地図入りの布団を縁側に引き出した。テツオの寝小便は誰もが知るところであった。
起床から、寮の玄関前集合まで五分で完了しなければ、玄関前でまた班が恥を曝さなければならない。森の吹く集合ラッパが響き始めた。ススムは見回りに来る先生の目を考えて、一渡り部屋の状況を見回すと、班員達を急かせて玄関に向かった。
玄関前の点呼が終わると、男女の順に二列縦隊で一行は登りの続く砂利道を妙義神社へと向かった。途中で第二寮、第三寮の生徒たちの隊列とも出会った。月に二度、三つの寮の合同の朝礼がもたれるのが定例であった。今日の進行はススムの号令で行われる予定であった。ここの号令は各寮の生徒代表が交代で行う、気は重いが晴れがましい舞台でもあった。
鬱蒼と繁る樹木が境内を厚く取り巻き、靄を含む朝の空気が、ススムの甲高い声を吸い込んで行った。
「気をつけ。寮長先生に、頭、中ッツ。直れ。」
号令の合間に、ススムは寮長の隣に顔をしかめ、生徒全体を睨め廻すようにして立っている坊主頭で黄土色の制服を着た男の顔をちらっと眺めた。顔つきに特に変化はない。ススムは少しほっとした。号令の掛け方が少しでも気に入らないと露骨に嫌悪感を顔に出す男で、「軍属」と呼ばれていた。それがどんな身分を表すのか子供らには判らなかったが軍隊から来た人間で、疎開生活を監視している怖い人と考えているようだった。
寮長の号令で「宮城遙拝」(天皇の宮城のある方角を向き拝むこと)を行った後、再びススムの号令に戻った。
「疎開児童へのお歌斉唱・・・」
子供たちの声が、境内の地面を這うように沸き起こり、次第に高まり森を越えて、遠く岩山の彼方にこだまして消えて行った。何処か誇らしげな歌い振りであった。ススムはこの歌を歌う時いつも一種の感動に浸っていた。
次の世を
背負うべき身ぞ逞しく
正しく伸びよ里に移りて
昭和皇后が疎開児童の身を案じて賜った詩歌として、子供らは徹底的に指導され、歌えない者は一人もいなかった。
雨で合同朝礼が出来ない時には、各寮の生徒代表が人員報告のために二寮に起居している軍属の岸教官の部屋に出向いた。ススムもこれまで一度だけ雨の中を傘をさして報告に行ったことがある。報告はいつも障子を閉めたまま外から声だけで行われるのが普通だった。
「第一寮、総員六五名。事故なし。現在員、六五名。報告、終わり。」
声が虚しく白い障子紙にぶつかって跳ね返って来ると、その向こうから濁ったくぐもり声が低く「よし。開けろ。」と響いて来た。ススムはそんな事は予想もしていなかったので、恐る恐る障子戸を開けた。その臆病振りを叱咤するように強い声が飛んだ。
「早くしろ。」
部屋の中はきちんと整頓していて、岸教官は制服のまま正座をしてススムを見据えていた。そばに日本刀が一振り立てかけてあり、彼の威厳を十分に演出していた。
「次の日曜日、一寮の生徒は勤労動員に出る。寮長の指示を仰ぎ生徒たちにしっかりと伝えておくように。」
「はい。」
「声が小さい。もう一度。」
「はい。」
ススムは、こんなに間近に岸を見るのは初めてであった。教官はやっぱり先生とは違う。全く違う。どちらも怖いが、怖さが違う。怖さというか、偉さというか。ススムは動転しながら転げ出るように二寮を跳び出し、雨の中を傘をさすのも忘れて自分の寮へ一目散に走った。
(八)
勤労動員とは、何をするのか、ススムには具体的には判らなかったが、今まで野菜運びとか、炭や材木の運び下ろし等をやった事があったので、何であれ、体にきつい仕事をやらされる事だと了解していた。炭運びの時は二人一組になって四貫俵を麓まで運ばねばならなかった。体の大きな者には八貫俵があてがわれた。背は高いが痩せているススムには荷が堪えた。背負ってから辛うじて立ち上がり、ふらふらと歩いた。使いつけない背負い子が肩にめり込んで、息が切れた。下の集積所に着く頃には、相棒のシュンタと四貫俵を背負った下級生二人に支えられ、歩くのがやっとの状態に疲労していた。荷を下ろすなり、しばらくは腰が抜けたように立ち上がることが出来なかった。
寮長に「軍属」の指示を報告したとき、「松の根っこ掘りをやるらしい。」と言っていたのを思い出した。
寮の前に集合させられた時、寮長はこう説明した。
「今、日本は最後の戦いを勝利するために国民がすべて力を出し合い頑張っている。今日の作業も、松の根から取る油で空軍の飛行機が一機でも多く飛べるように支援することになる。君ら小国民も国のために働くことが出来るのだ。」
山道を途中まで辿り、木こり道を抜けて着いた所は、切り口の新しい切り株が一面に並んだ、松林の跡であった。この辺りはこの間、材木の運びおろしをやらされたコースの上の位置に当たり、恐らくあの時の材木の切り出された松林の跡であろうと推測された。あの作業の時には、ススムの班では事故が起きていた。三メーター近い長さの材木の前後の先端に縄を結びつけ、それぞれに三、四人ずつが付いて山道を引きずり下ろして行ったのだった。カーブの所に来ると、材木の頭が谷側に突き出し、縄がぴーんと張った。前で綱を引く子供らは材木が谷に落ちないように山側に体を倒すようにして支えていた。そしてゆっくりと引き寄せながら、回り込むのに合わせて、後ろの綱が伸びて後部の端が谷側に突き出す。再び前が引き始めると、後ろが綱を引き寄せながら丸太を山道に合わせる。こうして苦労して広い道路の通る麓まで引き下ろしたのだった。そのカーブでの操作を誤って、後ろに付いていた五年のシンゴが綱に引っ張られて谷に落ち込んだのだった。幸い斜面を覆っていた藪に引っ掛かって止まったので、下まで落ちることはなかったが、仲間に助け上げられたシンゴの肩口には太くて長い野性の茨の刺が刺さっていて、ススムが丁寧に取り除いてやった。シャツにはべっとりと血が染みついていた。この事故の為に作業が遅れたことを説明した時、岸教官はシンゴの肩に一瞥をくれただけで、一言「不注意だからだ」と呟き、降りて来た別のグループの指導に向かった。ススムは、もっと他の言葉を期待していた。それがどんな言葉かは思い浮かばなかったが、シンゴにとても済まない気持ちになっていた。
既に二寮の生徒達は「軍属」の指揮で作業にかかっていた。
さほど大木に育った松の木を切り出したのでないことは、切り株の大きさからも明らかであった。しかし松の根は、土中深く根を張り、しっかりと大地を捉えていて、容易には掘り起こせない。株からかなり離れた所から掘り起こしに掛からねばならない。株の真下の根は太く、深く打ち込まれていて子供らの力では、地面から引き離すのは不可能に近かった。作業は捗らず、岸教官は苛立ち始めた。どの寮に割り当てられた箇所でも、まだ抜き取れた株は一つとしてなかった。
結局、午後まで掛かって、三個が掘り起こされたに止まった。教官は不機嫌な顔をして終了を宣言すると、生徒たちの指導を各寮長に任せて、引き上げてしまった。
寮へ帰ったススムは、休む暇もなく、秀子先生に呼び出された。秀子先生は寮長の太田先生と共に第一陣から派遣されている二人の女教諭のうちの一人である。まだ二十歳を越えたばかりの娘先生であった。
秀子先生は、寮長室を避けて隣の女子教員室へ入るように言った。同室の美和先生の姿は見えなかった。
「ススム君、この手紙は何なの。出した人は男の名前なのに、中身は女の子よ。返事は貴方の妹のタエちゃんの名前で書いてくれって。この子、余りいい子じゃないわね。」
カヨだ、ススムは起きた事を瞬間的に悟っていた。体中が火の塊になるように恥ずかしかった。すぐその場を逃げ出したかった。カヨならやりかねない。
秀子先生は、その封書の中の便箋を開いたままススムの前に置いた。ススムはそれを手には取らずに正座したまま視線を走らせた。カヨの字だ、綺麗に揃った丸っこい字が並んでいた。大人っぽい文章で、「早く会いたい。夢に見たりしている。あの上手な飛行機の絵を描いて送ってほしい。」といった文面が読み取れ、先生が言ったように返事の出し方が指示してあった。東京の町中から練馬に疎開して来た、あか抜けしたわがままなお嬢さんがそこにアグラをかいているように思えた。
「して良い事と悪い事と、ススム君は、判るでしょ。」秀子先生は話にくそうだった。ススムは黙って頷いた。
「わかった。手紙は持って行っていいわよ。」
「僕、いりません。燃やして下さい。」ススムの声は上ずっていた。少年は手紙をそのままにして立ち上がり、障子を開けて部屋を出た。目に涙が浮かんで来た。
当時、疎開地では文通の自由は認められていなかったのである。東京の空襲の状況等を詳細に学童に知らせることも、疎開地の食料不足の実態が、東京の家庭に知らされることも国策に沿ったことではなかった。戦意高揚を阻むものは一切禁止されていたのだ。子供らの受け取る郵便物はしばしば何行かが墨で塗りつぶされていた。当然彼らが書く家庭宛の手紙も、全文がそのまま肉親に届くことはまずなかったのである。ススムのところに届いたカヨの手紙も、そんな訳で先生の目にとまってしまったのだった。
ススムは、何故か無性に情けなかった。自分とカヨとの心の通い合いが、カヨの取った手段によって汚されてしまったように思えたのだ。惨めだった。そんな手紙は手にすることも出来なかった。勿論、カヨの丸っこい字をじかに手にとって見たい気持ちは十分にあった。自分の持ち物をまとめてあるリュックの底の方に密かに仕舞い込んでとって置きたい誘惑にもかられたが、偽りの方法に対する嫌悪が激情となってその未練を押し流してしまった。
一九四五年八月十五日のことであった。
前夜の「娯楽会」で、ススムは大活躍だった。「酒天童子」が鬼を退治する劇と、敵の飛行機を何機も撃墜し、片方のエンジンを破損してやっとの思いで基地に帰還する兵士を主人公にした劇を作り、仲間たちに役を割り振って上演にこぎ着けたのだった。勿論舞台もなければ幕もない、ぶち抜き教室よろしく三つの班の居室を襖を外してつなげ、その一角が舞台となる。観客の生徒も畳に座って、同じ平面での観劇である。生徒の気持ちを和ませようという教師たちの考えで、毎月一度企画されていた。ススムは仲間達と組んで、毎回二つ程の手作りの劇を作り、結構うけていた。教員たちも、この会の運営をススムや踊りの得意な菊谷ヨネを中心とする生徒達に安心して任せきっていた。
その時に小道具として使った、宿の長男の双眼鏡の立派さが話題に登っていた時、何か重大な話があって、昼近くに全員集合が掛かるという噂が流れ始めた。何故か、いつものように寮長から生徒代表を通して伝えられる正式な連絡とは違っていた。ススムの胸に感じたことのない不安が濃く広がって行った。宿の関係から流れた情報なのか、それにしても変だ、ススムは各班の部屋を走り回り、噂の出所を探った。その途中で宿の女将に呼び止められた。
「ススム君、今日はとても重大な放送があるんだって。」
重大なという言葉が異様な重さを帯びてススムを打った。
「先生からも話があるわよ、きっと。」と言い残して、女将は調理場に姿を消した。しかし、職員室には何の動きも起きず、ひっそりと静まり返っていた。
「先生達が、帳場に集まっているぞ。」
班長格の生徒が三人、ススムの所に注進に及んだ。ススムも一緒に玄関の方に向かうと宿の女将が、部屋の中に置いてあるラジオを大時計の横の小さな食器棚の上に乗せて、ラジオを聞きにわざわざやって来た二人の農家のおやじさん達に気配りを見せていた。教員達は目立たないように部屋の奥に座って、何かを待ち受けていたが、気持ちが外に持ち出されたラジオにある事は、傍目にも明らかであった。
「ガリ、ガリ、ピー。」という雑音が続いた後、突如この場とはおよそにつかわしくない、間延びがして、生活リズムを欠く甲高い声が流れ出した。大人達の顔が一瞬引きつったようにススムには思えた。息を飲む音が感じられ、寮長先生の喉がびくっと膨れ上がったのが見えた。ススムもラジオの声に耳を傾けるが、音質が極めて劣悪なだけでなく、ゆっくり流れているように感じられる言葉が難しくて内容が理解出来ない。ススムは思わず周りを見回した。秀子先生が大きな目を天井に据えるように見開き、形の良い唇を真一文字に結び、微かにえくぼの残る頬を引きつらせるようにして聞き入っている。瞬きを繰り返すうちに瞼のふちに涙が浮き出て来るのが見えた。ススムは、その様子から、放送の内容が、具体的な事は別として、とてつもなく重大なものであることを読み取った。胸が詰まって息苦しくなり泣きたい衝動に押し流されそうであった。
ラジオの音声を包む緊張がとけ、集まっていた人の姿がなくなって間もなく生徒達は、いつも娯楽会が開かれる女子の六、七、八班の部屋の襖を開け放し、そこに集められた。生徒達にもいつしか緊張感が伝わっていて、低学年の子供らの話し声だけが聞こえたが、それも初めだけで、寮長が話しだした時には、室内は既に静まり返っていた。
「君達、少国民までが親元を離れ、こうして頑張って来たが、・・・」
寮長の声は、一旦ここで途切れた。
「戦場の第一線では兵隊さん達が命をかけて戦って来た。お父さん、お母さんも銃後をしっかり守って来た。・・・」
ここで再び寮長の声がかすれた。
「ところが、最近、広島と長崎に新型の爆弾が落とされ、多数の死傷者が出た模様で、天皇陛下の・・・」
寮長は、姿勢を正し、顎を引いた。
「ご判断により戦争を終結することになりました。」
うわずった声で後を続けた寮長の語調は急に速くなっていた。
「日本は、米国に敗れました。戦争に負けました。戦争は終わったのです。今後、日本がどのようになって行くのか判りませんが、動揺、混乱することなく、先生達の指示に従って下さい。」
言い終わると、寮長はがくっと首を落とした。上級生の女子よりはむしろ男子の一部からすすり泣きが漏れ始めた。泣き声は次第に拡がり、ついには状況が全く理解できていない二、三年の子供らまでがつられて泣き始めていた。ススムを中心に六年生の何人かは、激しく畳をかきむしり身を捩って泣きじゃくっていた。その光景を前に、この場に居合わせた三人の教員たちは首を垂れたまま身動き一つしなかった。
(九)
妙義山は峨々たる岩山の連山である。子供らの宿舎から眺めると白雲山を中にして、左手に金洞山、右手に金鶏山が屏風のように立ち並んで迫って来る。黒い岩肌に、春は萌えぎ色の若葉が、秋には燃えるような紅葉が潤いと色彩を添える。もうかなり濃くなった緑が岩の骨格に衣装を纏わせている白雲山の中腹には白い大文字が日光を受けて鮮明に輝いている。この辺りまでは、子供らの日常的な行動範囲として、自由時間には野草取りや木苺摘みに出掛けて行くことが多かった。白っぽく色の変わった岩の上の登山道をたどって野ウサギのように身軽に登って行き木々の葉や岩影に見え隠れしながら姿を消し、甲高い子供の声だけがいつまでも響いていた。
ススムは、先に来ていた子供らの案内で、妙義神社の裏手から幾つかの石門を抜けて、第四門から轟岩、大砲岩を臨むルートを覚えてしまった。彼らは観光客ではないので、これは言ってみれば表通りであって、途中枝分かれした幾つもの生活ルートがあって、食料の調達、仲間達の秘密の会合など、重要な役割を果していた。山百合の球根、木苺の実、「木下藤吉郎」と名付けた雑草、蒜(のびる)、さらには木の下にとぐろを巻いていたり、笹原の中をさらさらと静かに滑るように移動する山かがし等も
彼らの獲物のメニューとなっていた。
ススムは、自由行動の時間を利用して、よく一人で山に入り、大文字の近くまで足を伸ばし、目を見張るような美しい実をたわわに付けた木苺の株を見つけたり、百合の群落に遭遇したりして、所謂「秘密の場所」を増やして行った。「秘密の場所」は誰にも教えず、そこでの収穫を突然仲間たちに差し出しては、羨望の的になるのも楽しみの一つであった。しかし、収穫期の終わりが近づき、実が腐りかけて来るのを知ると、親しい仲間を連れて行き、綺麗に後始末をつけるのであった。山かがしと一人で格闘し、手の甲を噛まれながら、何とか止めを刺したこともあった。この出来事は伝説を生み、ススムの評価は高まった。登山道をはずれた岩場で焚き火をし、蛇の肉を炙り、数名の「幹部」を招集して、貪り食った。飢えは未知の食材の不気味さを消してしまうのに十分であった。剥いだ皮は乾して、標本のように新聞で挟み、重しをかって平たく伸ばした。適当な大きさに切って、紐を付けると美しい栞になった。綺麗に仕上がったのが六枚も出来たので、男子班の班長にプレゼントし、残りの一枚を、一緒に疎開地にやって来た、あの浅井ミヤに手渡した。その時、周りに居たミヤの取り巻きの女の子達は、顔をしかめて「気持ち悪い」と言ったが、ミヤは、嬉しそうな顔をして、「へえ、鱗が綺麗ね。」と言って、蛇皮製の栞を見つめた。ミヤは、女子班のまとめ役をやっている。下級生の面倒見も良く、皆に姉のように慕われていた。勉強は、ずば抜けていて、この寮では誰も彼女に太刀打ち出来なかった。ススムも頭の良さでは、ミヤに一目置いていた。それよりもススムに話しかけてくるミヤの優しい語りかけ方が、ススムにはある種の母性を感じさせるのであった。大柄なミヤは、いつもススムを上から庇うような眼差しで見つめた。寮の中では、ススムとミヤは、ひやかしの対象ではなく、自然な一組のリーダーとして認められていたと言える。二人だけが手旗信号を操れるのも並外れた力量と錯覚されていた。少しだけませていて、父親とか兄弟から早い時期に仕込まれていたに過ぎないのだ。ススムは白雲山の中腹にある大文字の櫓に登って、丁度真下に寮の二階の窓が見通せる所に陣取ると、赤い旗を右手に、白の旗を左に持って、ミヤの部屋の方向に通信を送った。
「キョウモヤマハキレイ、キイチゴタクサントレタ、アトデアゲルヨ」
終わってから、読み取れたかな、と少し心配になった。肉眼ではやっと読み取れる距離で、この旅館の長男がもっている双眼鏡を使うと凄く良く見える、といつかミヤが言っていたのを思い出したからだ。ススムの自慢の手旗は長兄が作ったもので、棒の端から端まで一杯に布が付けられていて、握りの部分は布に切り込むように作られていた。ススムにとっては、ミヤと二人だけに判る秘密の伝達手段として使える掛けがえのない貴重な道具だったのである。ススムはいつも布の部分をしっかりと棒に巻きつけ、刀のように腰のベルトにぐっと差し込んで持ち歩いていた。ひとしきり山の空気に満足すると、ススムは山道を一気に駆け降りて行くのだった。神社の境内を突っ切ると、砂利を蹴立てて、二寮、三寮の前を駆け抜け、仲間のいる一寮へと駆け込んだ。
(十)
天皇の終戦の詔勅以後、生徒たちには張り詰めていた何かが姿を消し、イライラした気だるさが彼らを包んでいた。喧嘩も増えた。一層劣悪さをつのらせる食料事情が慢性の飢えと健康破壊を押し進めていった。詔勅の放送が流された日の夜、スムム達は、一部の生徒だけで会合を持った。「負けた国」の少国民はどうすべきかが、子供なりに熱っぽく語られていた。ススムは、宿の女将から、デマだろうがという前置きの後、アメリカ人が進駐して来て、日本を占領し、男は殺し、女、子供は奴隷にするのだと聞かされて、「このまま生きていて良いのだろうか。」と真剣に考えた。そのような考えの生徒は他にも居て「皆で屋根の上に登って、備前長船の鉛筆削りで切腹しよう。」という主張も真面目に語られていたのである。
子供らの生活態度は、日に日にすさんで行った。戦争の緊張に向かっていた一人一人の秩序意識が、荒々しい自然の中に投げ出されて、新しい流れに身を任せようとしていた。
その日、宿舎の前での朝礼で寮長の太田先生は苦虫を噛み潰した表情で生徒たちに向かった。喉に絡んだ咳払いが連発した。ススムは、何かあったな、と直観した。これは雷の落ちる兆候なのだ。
先生は、話始める前に、口の中で呟くようにしてから、いきなり「気をつけ」の号令を掛けた。
「大変残念なことがあった。よく聞け。昨日、土地のお百姓さんが来て、最近畑が荒らされて困っているという。トマトやじゃがいも、胡瓜にナスすべてが被害を受けているという。ここの生徒がやったかも知れないので、厳重に注意しておいてほしいと言うのだ。どうだ、お前たち。まさかそんな恥ずかしい事をやっている者はおらんだろうな。銃後を食料生産で支えてきたお百姓さんの足を引っ張るようなことをする奴は虫けら同然だぞ。やったことのある者は、潔く名乗り出よ。」
太田先生は、言葉を切って大きく息をついた。
子供たちの中には、密やかなざわめきが起こったが、すぐに萎縮するように静まった。「お前たちの中に、そんな人間がいるとは信じたくない。いいな、今後十分自戒して行動するように。終わり。」
最後の「終わり」が子供たちの横面を張るように鋭く響いた。
本土の空襲で、国内の流通網が混乱停止して、食料の供給が途絶えてしまったのか、その土地で調達できるものしか食膳に載らなくなった。群馬県は米どころでもなく食料事情は底をついていた。大麦どころか赤い固い殻皮のついたままの小麦や高梁などが米に混ぜられて、その混入率は日に日に高くなって行った。米粒の数が減ってきたのは子供らの食べ方の変化にも現れて来た。彼らは、米粒と雑穀とを食べる前に取り分け始めたのである。奇妙な食べ方が流行り始めた。中には、米粒だけを残し、匙を使って練り潰し、空き缶に詰めて、夜、寝床の中で食べる者まで出た。心理的な遊びだったのかも知れない。おかずには、圧倒的に「こんにゃくの油イタメ」が多くなった。このあたりはこんにゃくの産地であった。みそ汁の具もカボチャの実ではなく、舌にざらつく葉や茎が、人参の赤い根の部分ではなく、線香花火の火花のようにちりちりと広がる葉っぱの部分が使われた。食べ盛りの子供たちの胃袋がおとなしくしている訳がなかった。詩情をたたえて口許に運ばれていた桑の実や、木苺の実は、今や空腹を満たすためだけの食物にすぎなかった。山百合は花ではなく、球根が奪い合いとなり、土手のノビロなどは育ちきらぬうちに毟り取られた。名も知らぬ雑草も、適当に命名されて、野菜の仲間に加えられた。大木の下に繁茂する、ほろ苦い味の草は「木下藤吉郎」と呼ばれて大切にされた。とぐろを巻く蛇すら心地よい昼寝ばかりもしていられなくなって来た。
甘いものは全くなかったから、歯磨き粉や黄色の絵の具を舐める者もいた。
山の獲物よりももっと手近にある畑の作物が、狙われるようになるのも時間の問題であった。トマト、胡瓜は勿論、じゃがいも、さつまいも、農家の庭にある梅の木の実までが標的であった。こうした食の自衛行動がやがて子供らを飢えた徒党へと追いやって行ったのである。
木苺の実や百合の根など自然の産物だけでは間に合わなくなると、ススムは特殊部隊を組織した。農家の畑に見張りを立てながら入り込み、トマトやキューリ、じゃがいもを盗んだ。ススムは皆に「一本の苗を丸坊主にするな。なるべく多くの苗から一、二個ずつ実を取れ。」と言いつけておいた。その方が盗みが目立たないからであったが、その位のわがままは許して下さい、という気持ちでもあった。一度だけ現場を押さえられたことがあったが、涙を流して「皆に責任はないんです。僕がやらせたんです。余りにお腹が空くので食べさせたかったんです。ごめんなさい。恥ずかしいことをしてしまいました。お百姓さんの苦労も忘れて・・・」と素直に謝るススムの姿に、ゴボウを掘る長い鉄棒を手にしたいかつい農夫も初めの剣幕を忘れて見逃してくれたのだった。しかしススムの心の中は屈辱で煮えたぎっていた。優等生ぶった小利口な言い訳がまるで娯楽会の芝居の台詞のように思われて、ますます屈辱は内向していった。その後も大きな農家の梅の実を狙って行動を起こした。物音がかき消される程風の強い日を選び、たわわに実る梅の枝に一斉に石つぶてを浴びせる。少しの間沈黙を守り、小柄な少年を垣根の隙間から庭に侵入させて、落とした梅を、何枚も着込んだ上着のポケットに詰め込んで無事帰還させた。梅は青いまま齧る者もいたが、かなり大量でもあったので、宿の裏庭から失敬した風呂の古い小桶に、竹を組んで作った蓋を被せ、上から山で拾った大きな石を数個乗せて重しにした。残ったゴマ塩や調理場から手に入れた塩をぶち込んで秘密の縁の下に隠した。しかし漬物らしい味になる前に中身は殆ど無くなってしまったようだ。
農家の再三の被害届けと指導要請に、寮長は語気も鋭く子供らに警告を与えた。
「そんな泥棒行為をする奴は、虫けらだ。いや、虫以下だ。恥を知れ。」
そんな注意のあった後、ススムは仲間に、
「そうだ、俺たちは虫けらだ。虫だから野菜を食うんだ。なあ、皆。虫なんだぞ、俺たちは。」と言って、再び畑に忍び込み、今度は実や芋をもぎ取らずに枝や茎に付けたまま、虫のように這いつくばって直に食らいつく食べ方をしてみせた。皆も面白がってそれを真似た。子供らの口の周りは泥と汁とで無残な化粧が施されていた。
しかしこうしたすさんだ生活の中で子供らの心は荒れ、仲間同志の結びつきを失い、グループ間の抗争が増えた。主導権を握った者達が、力を誇示する為に他の者から、米飯やおかずを奪ったり、お碗を回して、中にご飯を少しずつ入れて供出するように強要することまで行われ始めた。ススムも野良犬の群れの一匹となって、屈辱感を冷静に見つめることを忘れ、それに埋没し火のように燃えながら落ち込んで行くのだった。
(十一)
調理場から金属の器に盛られたコウリャン入りの「赤飯」と南瓜の葉を具にした薄い味噌汁の椀、それに黒っぽいこんにゃくの油炒めなどを乗せた金属のお盆を運ぶ子供等の足音がひとしきり廊下を賑やかに往復する。この頃は食事の準備には、寮母も教師も立ち会わず、すべて子供等だけで行われた。食事ラッパが鳴り始めると、三つの部屋の襖が一斉に開け放され、八本の粗末な長テーブルが向かい合わせに並べられる。その端に家庭用の平テーブルが置かれた。ここにはススムやショウイチなどボスグループが座る.それも自分たちで並べることはない。必ず下級生にやらせるのだった。彼らは匙を磨いたり、ふざけあったりしながら時々下級生の働きぶりを監視していた。そばにラッパ手のリョウタが馴れ馴れしい態度で仲間に加わっていた。隣のショウイチが苦々しい顔をして、時々リョウタを睨んだ。(この野郎、この頃態度がでかいんだ。ラッパ吹けるのを鼻にかけやがって。)
決闘事件以来、ショウイチはすっかりススムと仲直りをして、ススムの言うことには逆らわなくなった。「俺はいつでもお前を守ってやる」そんなあからさまなショウイチの追従がススムの耳に甘く響いた。ショウイチがススムの肩を叩いて廊下に連れ出した。
「ススム、この頃リョウタの態度がでかいと思わないか。」
「まあ、少しはな。ラッパのせいだろ。」
「度が過ぎるぜ。チビたちに足を掻けとか、水汲んで来いとか、やたらえばり散らしている。今のうちに叩いて置かねえとまずくねえか。」
「好きなようにしろよ。」
やがて、食事の準備が整い、全員が席に着いた。「頂きます。」の合図は交代で全員が担当していた。端に座っていた下級生が小さな声を出した。
「声が小さい。」ススムが怒鳴った。箸を取ろうとしていた者がびくっとして慌てて箸を置く。一瞬ススムは自分の声が、いつか聞いた軍属の岸教官の声に似ているような気がした。
やがて食事が開始される。ラッパで始まった割には、食事の進行は遅い。終わりになることを避けているようにのろのろと食物が口に運ばれる。箸で米と雑穀の粒とを分けている者もいる。雑穀の粒だけを先に食べてしまい、米の粒だけを用意しておいた小さな蓋の付いた缶の中に匙を使って詰め込む。皿の上で匙で念入りに潰して糊のようにしてしまう者もいる。話し声がないのが無気味な雰囲気を作り上げる。黙々と食べているのではなく、黙々と終了時間を遅らせているのであった。
「供出。」立ち上がったショウイチが押し殺した声でにらみをきかせると、赤い塗りのお椀を長テーブルの端から廻した。下級生たちは上目を使ってボステーブルの様子をうかがいながら、一塊の飯を自分の皿から椀に移す。しばらくは送られてくる椀を無視して、黙って口を動かしている者もいる。
椀に何も入れずに隣の席に送った者がいた。シュンタだった。
「こらっ。」ショウイチの声が飛んだ。ススムもぎょっとしてシュンタを睨んだ。目は苛ついて険しかった。ショウイチの行動には抵抗を感じながらも、彼に逆らう者の出現には警戒心を持つようになっていた。
シュンタは既に廻した椀に申し訳程度のご飯を載せた。
ボステーブルに、赤い椀が戻って来る頃には、椀の中には仏飯のようにご飯が盛られていた。ボステーブルの三人の皿に、ショウイチが供出ご飯を分けた。心持ちススムの皿に大きな塊が載せられた。
食事は黙ってだらだらと続けられた。
何日かして、ラッパ手のリョウタが下級生たちに総殴りにあう事件が起きた。教師たちの耳に入り、事情聴取が行われたが、ラッパ手があまりに下級生に酷い態度を取ったのが理由とされて不問に付された。
「チビたち、泣きながら殴ってたぜ。可愛いったらねえの。」
ススムに報告にやって来たショウイチは、自分の思惑通りに事態が進んだのに興奮してか、頬を紅潮させていた。ススムはショウイチの口ぶりに嫌悪を感じながらも心のどこかでほっとしていた。
ススムは気持ちの置き場所に困って、付きまとうショウイチを避け、離れた四班の部屋をのぞいてみた。何やら賑やかな輪が出来ていた。扁桃腺の薬を噛むと口の中が真っ赤になると言って大騒ぎをしていたのだ。ススムが入って行くと、班長のタケゾウが騒ぎの理由を説明した。タケゾウはおとなしい性格で、ショウイチやススムの苛めの対象になることも多く、酷い時には正座をさせられた上に水の入ったバケツを膝に乗せられ、脛の下にそろばんをあてがわれ、いわゆる算盤責めに遭ったことさえあった。中世の拷問の真似事である。こんな不祥事にも教員の目は届いていなかった。
「どら、かしてみろ。」紫色をしている錠剤をススムは口に抛りこんだ。粒は歯にコリコリと音をたてて砕けた。軽い刺激が唾液の分泌を促して口の中に広がる。突如周りで見ていた仲間たちが大声を上げた。
「すっげえ。真っ赤だぞ、ススム。」
「ほんとかよ。」
ススムは、近くの流し場へすっ飛び、鏡を見た。口腔は真っ赤に染まり、まるで喀血でもしたか、人の血をすすったかのように、赤い唾液が唇の外にまで流れ出ていた。一瞬ススムの頭にやけっぱちな悪戯が思い浮かんだ。ススムはすぐに近くで鏡を覗きこんでいる仲間に、ショウイチを呼んで来いと命じた。ツバメのように飛んで来たショウイチと悪巧みが成立するのに時間は掛からなかった。
凄味を出すためススムは、さらに錠剤を五、六粒口に追加すると慌てて噛み潰した。そうしながら計画を頭の中で練り上げた。ショウイチに肩車の用意をさせ、言いつけ通り運び込まれたシーツを自分の首に巻いてショウイチの肩にまたがった。ショウイチが立ち上がると、のっぽの白い幽霊が出来上がった。上に乗ったススムが大きな口をがっと開くと、白い幽霊の口が朱に染まった。取り囲む仲間が喚声を上げた。すると突如ショウイチがふらふらと歩き出した。シーツで目が見えないのでよろよろしている。既に夕方になっていたが節電のために明かりはぎりぎりまでつけないのがきまりであったから、薄闇に浮かぶ二人が演出する姿は結構迫力ある効果を発揮していた。思わぬ反響にススムは狼狽したが、ショウイチはそのまま寮学習中の女子班の部屋に乱入してしまった。金切り声を上げて女生徒たちが部屋を逃げ出した。女生徒の叫び声は向かいの棟の二階まで響き渡った。
階段を駆け降りて来た教師たちに現行犯で捕まったのは、ほんの数分後のことである。慌てて水道の蛇口を咥えるようにして証拠隠滅を図ろうとしたススムも顔中に紅が廻った状態で御用となった。
二階の職員室の廊下で二人が幽霊の姿を再現させられていつまでも立たされている姿が、向かいの女子の部屋からよく見えた。窓越しに、妹のサエコを呼ぶ声が聞こえ、「お兄さんが大変だよ。」と告げる声が高まりながら女生徒の姿が窓辺に固まり始めていた。
寮長の太田先生は現場を押さえるとすぐ、「もう一度同じ格好をせい。」と言いつけて、薬を噛ませ、シーツを着せて、肩車を組ませた。そして、いいと言うまで立っていろと命じたのだった。「ススム、さっきやったように口を大きく開かんか。」
「僕が悪いんです。ショウイチは悪くないんです。許して・・・。」
疲れて次第によろめき出したショウイチの背でススムは泣き声を出し始めた。ショウイチもシーツの下ですすり泣いていた。女生徒たちが向かいの二階の手すりに群がって、何か言い合っているのが見える。ショウイチには見えないが、ススムには言葉まで聞こえそうだ。耳元まで熱くなって屈辱に耐えた。寮長は楽しそうに口元に笑みを浮かべながら、「もう少し懲らしめた方が良かろう。」と考えていた。
(十二)
夜の班学習の時間が終わり、九時の点呼が済んで就寝前の一時であった。早めに布団を敷き寝ころがって居る者もいた。夕食のご飯を練って小さな缶に詰めたのを、匙でちびりちびりと舐めるように食べている者もいた。歯磨きの粉で愛用の匙をぴかぴかに磨いている者もいた。自分の虱を生け捕りにして、仲間と廊下の継ぎ目をコースに見立てて競争を楽しむ者もいた。手でばたばたと床を叩き、脅すようにして虱を這わせるのである。中にはコースを横切ってはみ出してしまうのもいて、観客と虱主とをはらはらさせた。
それなりにのどかな風景であった。
「おーい、柴田兄弟が居ないぞ。誰か見たものいないか。」
突然、大声が上がった。
「さっきの点呼の時は居たぞ。」それは班の皆が確認していた。
「靴がないぞ。」
玄関の方でも声が聞こえた。兄弟の所属している二班の班長、ヒロシが顔を引きつらせてススムのところにやって来た。
「ススム、どうしよう。」
「一緒に、職員室に行こう。」言いながら、ススムはもう二階に通ずる階段の方に歩きだしていた。ヒロシが続く。
報告を受けて、寮長が生徒を全員集めて状況を把握すると、すぐに決断した。
「松井田方面を捜索する。男子の各班長、一緒に来い。駅へ出る道を探す。大きな声で名前を呼びながら走れ。多分あの連中も走ってる筈だ。左右の桑畑をよく見るんだ。物音にも注意しろ。判ったな。」
寮長は、宿の女将から大きな御用提灯を借り受けると、それをススムに持たせ自分は軍用の懐中電灯を握りしめて先頭に立った。ススムと男子班の班長たちがその後に続いた。
「遅れずについて来い。」
ススムは提灯の重さよりもその大きさに戸惑いながら、足元がもたついたが、懸命に寮長の後を追ううちに慣れてきた。追手の一行は周りに注意を払いながら小走りに走った。
「春太、シュンタ・・・。」夜空に子供の声が遠くまで響いた。坂の上の黒門が後ろに遠のき、農家の軒が姿を消すと、桑畑の中に細く長く続く一本道を、一行は走り続けた。左右の桑畑は黒い海のように深々と広がっていた。屈み込むと葉の重なりの薄い所から灰色の夜空が透けて見えた。そんな背景にシュンタ達の丸い頭の影が地に伏せて浮かび上がって来るような錯覚に、ススムは何度もおちいった。そして遂にそれが現実のものとなったのだった。
「止まれ。」誰かの声が響いた。「泣き声が聞こえる。」
一瞬追手の一行はぴたりと足を止めて、息を凝らした。ススムが桑の葉の下に潜って、提灯を差し込むように畑の奥を照らした。弟シュウジの小さな背中を上から押さえ込むように抱いて、右手で泣き声が漏れるのを防いでいた。目だけが提灯の光を受けてキラリと光った。寮長が飛び込んで二人を抱え込むと「お前たち、何で・・・。」と怒鳴ってから、声を詰まらせた。
追手の気配を背後に感じて、逃亡の失敗を悟った兄は、泣き始めた弟の声を聞かれまいとして、茂みに潜み、弟の口を押さえて追手の通過を待っていたのであった。
捕らえられた二人だけではなく、何故か捕まえた側の子供達も泣きじゃくっていた。寮長までが悲痛な面持ちで、時々シュンタに話しかけて逃亡の動機を知ろうとしていた。
「もう誰も信用出来なくなったし、体の弱い父親のことも心配だった。弟だけを置いて行く訳にもいかず、一緒に連れて逃げた。でも途中で弟は走れなくなった。べそをかき始めてしまった。俺一人だったら線路を伝ってでも逃げられたのに。」
シュンタは、途切れ途切れに呟くようにこんな意味の事を語り出した。ススムは碓井川にかかるあの大きな鉄橋を一人で渡って行くシュンタの姿を想像した。ススムは長いこと記憶の外に追い出していた母の面影を久しぶりに思い起こしていた。
一行は、前方の闇の中に見えて来た黒門坂を重い足取りで登って行った。登るにつれて寮の二階の灯が見えた。ススムの気持はもう現実に戻っていた。皆がどんなに心配していることだろう。「帰って来たぞう。」今にも叫びだしたい気持ちに駆られていたのだった。
(十三)
秋も深まった頃、全国に散らばっていた東京の疎開児童達は、ぞくぞくと荒れ果てた東京の親元へと戻って来た。ススムの学校も焼失していた。しばらくは被災を受けなかった近くの商業学校に間借りすることになっていた。
ススムの家は運良く焼けることもなかったが、家具は福島に疎開してあったためか、リンゴ箱などが、テーブル代わりに使われており、茶の間には手製のルンペンストーブが据えられてあった。その前でススムは「欲しがりません、勝つまでは」という大きな宣伝ポスターの裏に、戦闘機零戦の絵をでかでかと描いた。寮の学習時間は殆ど自習だったので絵ばかり描いていた。自分もやがては航空兵となって大空を駆け巡るつもりでいたこの飛行機のことは細部に至るまでよく覚えていて、鉛筆は滞ることなくすらすらと動き続けた。ススムは、ふとカヨのことを思い出した。
「これお前に描いてやりたかったのに、馬鹿な奴・・・」
帰宅した日の晩、母親が作った歓迎の夕食は、ルンペンストーブで炊いた、じゃがいもの沢山入った「芋飯」だったが、そのふっくらとした白さと、立ちのぼる湯気の優しさを見た時、ススムの目には涙が滲んだ。
「旨そう!」
飛びつき、茶碗を斜めにかき込み始めたものの、ススムは間もなく茶碗を置いてしまった。胸が詰まって飯が通らないのだ。
「慌てないでゆっくり食べなさい。」傍で母親が笑いながら言ったが、食事が通らないのは、感激してとか、あせったためにそうなったのではなかった。今までの食生活の後遺症で多量の食物が入らなくなっていたのだ。箸を置いて胸を押さえ、下を向いてしまったススムの姿に、初めは笑っていた母も、黙って目頭を押さえた。子供に苦労させたという思いが、自分を責めたてているようであった。
栄養不足のため痩せこけ、皮膚病に犯されたススムの体を回復させるために、母親のした努力は並大抵のものではなかった。衣類を完全煮沸して虱退治をしたが、一度や二度では、卵が死なず、虱はなかなか死に絶えなかった。「ひぜん」と呼ばれる皮膚病はそれ以上にしつこくて、硫黄の薬品を塗り、何度も皮膚が剥げ、少しずつ治癒して行った。何よりも母を驚かせたのは寄生虫であった。ありとあらゆる虫下しを求めてススムに与えた母親は、ある日便所でススムが大声を上げるのを聞いたのである。
「母さん、白い、白いウンコが出た。」
便器を覗き込んだ母親の目に映ったのは、絡み合ったままうず高く排出された回虫の死骸であった。「ススム、出たんだよ、虫が出たんだよ。もう大丈夫だ。」母親は泣きながら叫んだ。ススムの顔から脅えが遠のき、明るさがとって代わった。
その後、ススムの体力は目立って回復し始め、体重も増して行った。「ひぜん」の痒みも薄れて、気性までが元通りに回復して行った。
母親は、毎日のようにススムから疎開生活の状況を聞き出し、母なりに現地の様子を納得しようと努めているようであった。
帰京する直前は病人が多発して、点呼の時にも、「第一班総員十名、事故七名、現在員三名、報告終わり。」というような報告が増え、病人の布団が並んでいる中で、二、三人が起立して点呼を受けるという状況だった。殆どが、慢性の下痢を起こしていたが、便所の前で人に排便の音を聞かれて、「あいつも下痢だ」と判ると、食事を減らされるので、誰もが症状を秘密にした。教員も同様に苦しんでいることを、子供らも知っていた。密偵ごっこのように職員のトイレまで彼らの手は伸びていたのだ。四班の班長タケゾウは重症の大腸カタルを起こしていて、後で判った事だが、引き上げがもう少し遅れるようであれば、生命も危険だったということだ。
母親は、ススムが日記代わりに付けていた毎日毎食の献立記録を丹念に読んだ。「小麦の丸粒なんて消化する訳ないでしょう。」米と小麦やコウリャンの比率を克明に記録してあるのを見て、胸が痛んだ。みそ汁の具まで記録されていた。人参の葉、カボチャの葉、さつまいもの蔓。記録の終わりの頃のおかずは、圧倒的にコンニャクの油炒めが多かった。群馬は産地なので、これだけは豊富だったようだ。それにしても、この食に対する子供の執着。非合法化されつつあった労働運動に関与し生活も安定していなかった夫との生活の中で貧乏の辛さはさんざん知り尽くしている母親にしてみれば、ススムのいじらしさが悲しい程身に染みた。
こうしてススムの身も心も回復して行ったある日、かっての疎開仲間から呼び出し状が届いた。話があるから体育館の裏手に来いと小さな紙切れに書いて、ススムの机の上に置いてあった。
ススムはずっと前から持っていた予感が今的中するのだと思った。疎開地から引き上げてからは、疎開仲間は苦労を共有して来たにもかかわらず、何故かよそよそしい間柄となっていた。ススムはいつも強い関心を注がれながら、それでいていつも避けられているように感じられた。話をするのも主に縁故疎開から帰って来た子供が多かった。それで心が和んでいたわけではなく、自分でも一番気になるものから逃避しているような不安感が付きまとった。
「いつか、何かあるな。」
ススムは、そう思っていたし、むしろそれが早くやって来ることを心の何処かで待ち望んでいるようにも思えた。
春とは言え、卒業式を待つ時期のグランドはまだ底冷えがする。体育館の裏は冷たい影が拡がり、その隅に六人程の生徒が背を丸めて立っていた。近づいたススムに気づくと、全員が顔をこちらに向けた。輪の中にショウイチの顔が見えた。興奮して歪んだ顔に、うすら笑いを浮かべてススムの方を睨んだ。ショウイチがススムに近寄ると、他の少年たちも付き従うように続き、ススムとショウイチを中にして円陣を作った。
ススムは妙義の疎開地で、ショウイチに決闘を挑まれた時のことを思い出していた。あの時も取り巻きに囲まれての対決であった。部屋の中と外の違いはあっても、まるで同じ場所での出来事のように思い出された。それもついこの間のことのように思われた。
「よう、ススム。疎開じゃ、よくも好きなようにやってくれたな。みんなお前を恨んでる。今日は存分にやらせて貰うぜ。悪く思うなよ。」
ススムは、周りを囲んでいる連中がさっと散って、ショウイチが前に乗り出して来るものとばかり思っていた。しかし時代が代わり、ルールも変わっていた。ススムを取り巻く集団が一気に同時に襲いかかって来たのである。声を出すことも出来ず、拳の雨と容赦のない足蹴りの中でススムは次第に意識が遠のいて行くのを感じていた。遠のく意識の中で、いくつかの言葉が切れ切れに記憶に残った。
「この野郎。よくも人の飯取りやがったな。」
「でけえ面しやがって。」
「先公とぐるになりやがって。」
「謝れ、馬鹿野郎。」
ほっぺたにひやりと冷たい地面を感じて、ススムは意識を取り戻した。起き上がろうとしたが、体があちこち痛んで、容易なことでは身動きも出来なかった。しばらくは、ごろごろと地べたを這い回っていたが、やっとの思いで上半身を起こした。唇は切れ、血が顎のあたりまで流れていた。鼻血で鼻が詰まり息苦しくて咳き込むと、唾は真っ赤に染まっていた。ススムは背中を丸めて頭を抱え込んだ。頭のあちこちに瘤が出来ているのが掌に感じられた。「ふーう。」と大きく息を吐いてみた。鼻先で赤い風船が弾けた。
思えば、ススムの方からは手出しは何一つ出来なかった。いや、する気がなかったのかも知れない。復讐の始まる瞬間、ススムのどこかで「やっぱり、来たな」と納得していたように思ったのではないか。来るべきものが来て、今ほっとしている。そんな妙に静かなものが心の中に生まれていた。不思議な位に涙が出なかった。謝ることもした記憶はない。ただ黙って天罰に耐えているようであった。
ススムは教室に戻るのを止めて、そのまま家路についた。鞄をそのままにして帰宅すれば、家でも、学校でも騒ぎになるかも知れない。しかし、どうしてもこのみっともない姿で教室に姿を見せることは出来なかった。家までの道を歩きながら、学校からの問い合わせにも、母親からの詰問にも「男の子の世界によくある一寸した喧嘩だ」ですまそうと心に決めていた。相手の名前も明かすまい。台風が過ぎて行ったようなものだ。それでいいんだ。幸い鼻血も止まり、左足が痛んでびっこを引いているものの、何とか歩けるのにススムはほっとしていた。
「これは俺だけの秘密だ。」そう呟きながら、ハンカチを舐め舐め、顔や手足の泥と血の汚れを拭った。母親に「一寸した喧嘩だよ」と言ってごまかせる程度に、セーターやズボンの汚れも落とした。顔の腫れはどうしようもないな、と手で触れてみながら苦笑していた。俺だけの秘密。そう言えば、カヨの手紙のことも誰にも話してなかったな。あれも俺だけの秘密だった。カヨはあのまま縁故疎開から戻ってきていない。ススムは真っ直ぐ家には向かわず、裏手の道を畑へと向かった。下の畑は、麦の芽が太く強く育ち、日に日にその緑の厚みを増していた。畦道を歩きながら、韮虫のことを思い出した。また、実った黄金色の波の上をヤンマが悠然と飛行するのが見られるだろう。あの上の畑との境には見上げる程にトウモロコシが生い茂る。そしてその葉の上でしばし憩うカミキリやクワガタが姿を見せるだろう。運が良ければ、虹色に光を放つ玉虫に出会うこともあるだろう。この手に捕ろうと指先を伸ばすと、突然大きく翅を広げて優雅に飛び去ってしまうかも知れない。
ススムは、幼い頃美しく刻まれたいくつもの自然との出会いを、アルバムを拡げるように思い描くのだった。それを閉じるように足を止めると、口を真一文字に結んで、畦道を真っ直ぐに我が家へと向かうのだった。

(完)
|