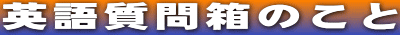
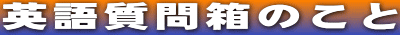
| 定年退職後、嘱託の時期も入れて、通算43年間現場で英語を教えて来た私にとって完全退職するに当たって、これからもこの経験を活かす方法はないかと考えて、ホームページに、「中高生英語質問箱」の設置を試みたのである。今では、二つになったホームページのどちらにも置かれている。 やはり質問者の多くは、受験生である。受験に結末がつくと、終わりになる。質問の仕方も様々で、自分である程度の答を出して来て、これでいいのか、というのもあれば、ただ問題を並べて送ってきて、答を教えろという感じの物もある。質問箱を始めるに当たって、僕は二つの原則を立てた。謝礼の問題と質問の仕方の原則である。 安かろう悪かろう、という言葉通り、継続的努力には、お互いに投げやりが付きまとうし、こちらも解答を用意し、分かり易い説明を工夫するのにはそれ相当な時間を費やす、つまりそれだけの労働をする事になる。電話代も掛かる。慈善的なボランティアという考えもあるだろうが、僕の場合は、自己申告による謝礼制を採用する事にした。何度か無料で利用して見て、この人にくっ付いていて、ずっと利用して行こうと考えたら、自分で「月に幾らくらいが妥当」と決めて、それだけの金額を振替で送ってくる。人によって、切実度も違えば、経済状態も異なるだろうから自分で決めるのが一番良い。そう考えたのである。 「そんなこと言っても、只で利用されるだけで、だれもお金なんか送ってきやしないよ。」内のカミサン始め皆がそう言った。 実際に質問者が現れると、僕は嬉しかった。「説明が分かりやすい。」などとお世辞でも言われようものなら、にこにこしていたものだ。一人に1時間以上も掛けて、解答を作り上げる事もあった。答えの原則として「即座に」というのをモットーにした。勿論出かけていたりすれば、夜になってからという場合もあったが、大体が夜遅くの質問が多く、それを翌日の朝までには答えておくようにした。敏速さと分かりやすさを売り物にしたかった訳である。これは確かに好評であった。 質問者への要求は、謝礼は自己申告であるから自由なので、質問の仕方に絞られた。「生きたアンチョコにはならないよ。自分で考えたところまでを率直に書いて来なさい。分からない所を指摘しなさい。そうすると質問者の理解の状態が掴めて、おのずと教え方が見えてくるのだから。」というのをその原則にしたのだ。これは質問者にとっては小うるさい注文だった様だ。それで辞めてしまった者もいたようだ。 問題集から写したのか、学校の宿題なのか、問題だけが書いてあって、「全然分かりません。全訳を教えて下さい。」的な質問は、1度は突き返して、「自分で分かる所まで考え、一応の答を作ってご覧。」と要求した。これで諦めて来なくなる者もいたが、「分からないから聞いているのだ。」と居直るものも、「考えたのだけど分からないから全訳を教えて。」と懇願する者もいた。時には教えたこともあったが、そんな時には、「今使っている問題集、今受けている授業は、君には程度が合っていない。自分で三分のニは分かるような教材を使う事が大切だよ。」というアドバイスも添えてやった。僕は、教えると言うことの意味を一つの人間関係の発展と考えて、教師をやって来たつもりだ。知識の切り売りは、学習者をも駄目にしてしまう。「理解」ということは、もっと心の繋がりを意味するものと考えて来たのだ。 「それで・・・。」と気になる次の質問が咽喉まで出かかっている読者も居られるのではないか。そう、謝礼の方はどうなったのという点である。 原則を読んでいないのか、知らぬ振りをしているのか、全く謝礼には触れることなく、何回でも質問し「早くて、良く分かる」と愛想の良いメールを寄せて来る。このタイプには、「全部教えて」タイプが多いように感じた。熱心な女子中学生が母親との対話の中で謝礼問題に取り組んだ例を紹介して、終わりとしよう。 「こんなに何度も質問しているので、謝礼の事が気になっているのですが、母に相談したら、自分のお小遣いから出した方が一生懸命努力するんじゃないの。そうしなさいと言うんです。でも私の1月のお小遣いは少ないので、1,000円がやっとです。恥ずかしいのですがそれでもよいでしょうか。」と言ってきたのだ。僕は感激した。この子は本当にやる気になっているし、必ず向上する。勿論結構ですとも、と返事を書いた。 質問は、どんどん質が向上し、理解が深まって行くのが目に見えた。教えていて楽しかった。今流行りの言葉で言えば「双方向性」が実現したのである。勉強のことでのやり取りだが、そこには人間のやり取りが存在していた。その子には、今でも自分のHPの更新を、その都度知らせている。「質問箱」で稼ごうかと考えている方に参考までに付け加えるなら、こんな嬉しい質問者は極めて稀であるということだ。 (2001・7・2) |